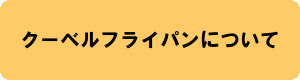「安いフライパンと高いフライパンがあるけど安いフライパンは品質が不安」
「安いフライパンでも長く使えるようにしたい」
フライパンの価格はプロ級から初心者用まで幅広く、価格はピンキリです。
その中でも、スーパーやホームセンターなどでは安いフライパンが大量に陳列されています。
そこで、本記事では、安いフライパンの選び方と使い方を紹介します。
また、ステンレスライパンをご検討の場合はクーベルのステンレスフライパンをご検討ください。
ステンレスは温まりにくく冷めにくい素材なので、食材を入れたあとも温度が下がりにくいという特徴を持っています。加えて、予熱を行うことによって油分を多く含む肉や魚などの食材は無油調理を行うことも可能で、余分な油とカロリーを抑えた健康に良いヘルシーな料理が楽しめます。
ぜひこの機会に、一生モノのフライパンをお手に取ってみてください。
価格が安いフライパンの特徴
安いフライパンは、手軽に購入できる点が大きな魅力です。
主にアルミ製でプレス加工された薄型のものが多く、軽量で扱いやすい特徴があります。
最近では、焦げ付き防止のコーティングが施された製品も多く、価格以上の機能を持つ製品も増えています。
コーティングが施されたフライパンは、日常使いで十分満足できる性能を発揮することが可能です。
さらに、安価なフライパンは手軽に購入できるため、試しに使ってみることも簡単です。
例えば新しい調理法を試してみることや、料理の練習用として活用できます。
特に初心者には、安価なフライパンは失敗しても気軽に買い替えられるため、経済的な選択肢としても優れています。
適切に選べばコストパフォーマンスの良い選択肢となりますが、頻繁な買い替えが必要になることもあります。
加えて安価なフライパンは初期投資が少なく済むため、特に一人暮らしやサブ用途として重宝されます。
安いフライパンのメリット・デメリット
フライパンなどの調理器具を扱っているお店やホームセンターなどでは、価格が安いフライパンから高いフライパンまでたくさん売られています。
安いフライパンでも高いフライパンでも、当然ながら製品としてはどの製品も一定の品質を保っています。
そのため、一見すると安いフライパンの特徴が見えづらい場合があります。
そこで、安いフライパンのメリットとデメリットを紹介します。
メリット|コストパフォーマンスが高い理由
安いフライパンの代名詞であるアルミのフライパンは、初期投資が少なく済むのが一番のメリットです。
最近では焦げ付き防止のコーティングが施された製品も多く、日常使いで十分満足できる性能を発揮することが可能です。
そのため、安価なフライパンは手軽に購入できるため、試しに使ってみることが簡単です。
加えて安価なフライパンは高価な製品に比べて失敗しても気軽に買い替えられるため、初心者にもおすすめです。
特に初心者には、安価なフライパンは失敗しても気軽に買い替えられるため、経済的な選択肢としても優れています。
デメリット|耐久性・熱伝導・こびりつきの問題
安価なフライパンは場所によって熱伝導性が異なり、ムラ焼けや焦げ付きが起こりやすい点が課題です。
加えて、コーティングの剥がれやすさや寿命の短さもデメリットです。
大抵のアルミフライパンでは表面がコーティングされているため、コーティングが剥がれないように強火調理や金属製ヘラの使用は避ける必要があります。
しかし、いくら丁寧に扱ったところで日々使っていればコーティングが剥がれてしまうため、買い替えを余儀なくされます。
安価なフライパンは高温に弱く、コーティングが劣化しやすいため、頻繁な買い替えが発生するのです。
特にコーティングが剥がれた状態で使用を続けると、金属部分が露出し、食材に影響を及ぼす可能性があります。
そのため、調理の安全性を確保するためにも早めの買い替えが推奨されます。
安いフライパンを選ぶ際のポイント
安いフライパンのメリット、デメリットを紹介した後は、安いフライパンを選ぶときのポイントを紹介します。
安いフライパンの中でも、寿命が長い製品や使い勝手が良いフライパンはあります。
ただ安いフライパンを選ぶのではなく、コストパフォーマンスが良いフライパンを選ぶコツを紹介します。
素材別の特徴(フッ素コーティング・セラミック・鉄・ステンレス)
素材によって特性が異なるため、自分の用途に合ったものを選ぶことが重要です。
フッ素コーティングは、焦げ付きにくく手入れが簡単で、初心者に使いやすいフライパンです。
ただし、耐久性は他のフライパンに比べてやや劣る傾向があり、特に高温調理は注意が必要になります。
続いて、セラミックを紹介します。
セラミックはフッ素コーティングよりも高温に強く、安全性が高いのが特徴です。
耐久性は高価な製品に近いものもあるものの、セラミックが割れやすい点に注意が必要です。
価格としてはフッ素コーティングよりも高い場合が多いため、価格と寿命を考えるとコストパフォーマンスは高いフライパンになります。
鉄は、フッ素コーティングやセラミックと比べて高熱調理に適しているものの、細かいお手入れが必要なフライパンです。
中華料理など高温調理が必要な場合は、鉄フライパンが最適になります。
しかし、フライパンの表面が無加工のためフッ素コーティングやセラミックと比較して食材がくっつきやすいという特徴があり、油を大量に使います。
加えて鉄は錆びやすいので、錆とりやシーズニングなど日々のお手入れが必要です。
最後はステンレスを紹介します。
ステンレスは鉄と耐久性に優れ、鉄よりも錆びにくい特徴があります。
そのため、お手入れは普通のフライパンと同じようなお手入れで問題ありません。
しかし、ステンレスは熱伝導性が今回紹介した中で一番劣っており、予熱から調理を始めるまでに時間がかかります。
加えてステンレスの素材によって価格が変わり、今回紹介した中では初期費用が一番高いのがデメリットです。
とはいえ一度購入してしまえば長く使えるフライパンが多く、長期的に見ればコストパフォーマンスに優れています。
厚みと重さのバランス|軽すぎるとダメ?
安いフライパンは軽量な製品が多く、軽量なフライパンは扱いやすい反面熱ムラが生じやすくなります。
適度な厚みと重量感を持つ製品を選ぶことで、調理中の安定感と仕上がりの良さを両立できます。
特に、厚みがあるフライパンは熱を均一に伝えるため、調理の成功率が上がります。
一方で、重すぎると非力な人は持ち上げにくくなるため、適度なバランスを見つけることが重要です。
厚みのあるフライパンは高温調理にも適しており、耐久性も高めです。
そのため、初心者には軽いものから始めて、慣れてきたら厚みのあるものに移行するのも一つの方法です。
IH・ガス火などの熱源対応チェック
IH・ガス火などの熱源対応チェックも欠かせません。
大抵のフライパンはガスには対応しているものの、安いフライパンの場合は価格を抑えるためにIH対応になっていない製品が数多く存在します。
そのため、調理する場所がIHの場合はIH対応かどうかを必ず確認しましょう。
IHコンロ対応フライパンは、底面が磁気というのが特徴です。
ガスコンロの場合は、底面が平らで安定している方が調理は安定するためおすすめです。
最近では、IHコンロとガスコンロのどちらにも対応するフライパンがあります。
両方対応しているフライパンであれば、どちらのコンロでも安心して使用できるため、引っ越しなども検討している場合は両方の熱源に対応しているフライパンがおすすめです。
安いフライパンを長持ちさせる使い方・お手入れ
安いフライパンは高いフライパンに比べて耐久性が低いケースが多く、定期的な買い替えが必要です。
とはいえ、1年もたずに買い替えるなどは好ましくなく、丁寧に使えば長持ちできます。
そこで、安いフライパンを長持ちさせる方法を紹介します。
強火NG!適切な火加減のコツ
安いフライパンであるアルミフライパンでは、食材のくっつきや焦げ付き防止のためフライパンの表面がフッ素樹脂などでコーティングされています。
コーティングは熱に弱く、強火で使用するとコーティングが劣化しやすいため中火以下で調理することがおすすめです。
加えて調理開始時にはフライパンを予熱してから油を加えることで、コーティングの劣化を防ぎます。
油は適量で問題なく、鉄フライパンのように過剰な使用は不要です。
調理中もフライパンの温度を常にチェックし、必要に応じて火力を調整することが重要です。
金属ヘラ・スポンジの選び方で耐久性UP
安いフライパンの寿命を延ばすためには、調理道具にも気を使うのが大切です。
フッ素コーティングのフライパンでは、金属製の道具を使うとコーティングが剥がれやすくなります。
安いフライパンを長持ちさせるためには、金属製ヘラは使わずシリコンやナイロン製のヘラがおすすめです。
加えて洗浄時にはスチールたわしや金たわしは使わず、柔らかいスポンジを用いることで表面を傷つけず長持ちさせられます。
洗浄後は水気をしっかり拭き取って保管することで、錆びや劣化を防げます。
特にフッ素コーティングのフライパンは、洗浄後に完全に乾かすことが重要です。
フライパンの保管方法では、他の金属製品と接触しないように保管すると長持ちします。
吊り下げ収納は、他の金属製品と接触しないだけでなく、フライパンが乾燥しやすくなるのでおすすめです。
コーティングを長持ちさせる洗い方と保管方法
フッ素コーティングのフライパンは、強力な洗剤や研磨剤を使うとコーティングが剥がれやすくなります。
特に研磨剤はコーティングの劣化を早めるため、使用厳禁です。
汚れが取れない場合は、クエン酸や重曹などを活用しましょう。
フッ素コーティングのフライパンは、湿気を残すと劣化が進む可能性があります。
そのため、フライパンは水気をしっかり取って乾燥した状態で保管しましょう。
例えば、フックを使った吊り下げ収納は長持ちにおすすめです。
安いフライパンの寿命と買い替えタイミング
安いフライパンは寿命が早く、寿命になったら買い替えが必要です。
そこで、フライパンの寿命はどういう状況かという点と、買い替えのポイントを紹介します。
焦げ付きやすくなったら寿命のサイン?
フライパン調理中に、食材の焦げ付きが頻発すると寿命の兆候です。
焦げ付きが増えるのは、コーティングが劣化している証拠です。
コーティングが劣化すると、焦げ付きが増えるだけでなく食材の味や安全性にも影響を及ぼす可能性があります。
また、焦げ付きが増えると調理に時間がかかるようになり、ストレスを感じることもあります。
フライパンの寿命は、食材がくっつきやすく焦げ付きが増えたと感じたら、買い替えを検討しましょう。
コーティング剥がれのチェックポイント
コーティング剥がれのチェックポイントは、以下のポイントで確認しましょう。
-
食材がくっつきやすくなり、焦げ付きが多く見られる場合
-
フライパンの表面に剥離や傷が見られる場合
コーティングが剥がれる栄養は、食材が焦げ付きやすくなるだけでなく、食材に悪影響が発生してしまう場合があります。
特にフライパンの表面に傷が見られる場合は、すぐに買い替えを検討しましょう。
コスパよく買い替えるタイミング
コスパよく買い替えるタイミングは、セール時期やキャンペーンの活用です。
特に大型スーパーやホームセンターではセールが頻繁に行われているため、情報をチェックしておくのをおすすめします。
オンラインショップの場合、セール期間以外にも割引クーポンが提供されることがあります。
適切なタイミングで買い替えることで、コストパフォーマンスを高められます。
加えて、オンラインショップでは製品の評価やレビュー記事が参考になります。
特にレビューは、製品の実際の使用感を知れるため、自分に合ったフライパンが見つけやすくなります。
よくある質問(Q&A)
安いフライパンについて、よくある質問をインターネット中心に調査しました。
安いフライパンを検討している人は、ぜひ参考にしてください。
Q1. 安いフライパンはすぐにダメになる?
安いフライパンでも、正しい使い方とお手入れを行えば長く使用できます。
強火調理や金属製ヘラの使用は避け、しっかり水気を取ってからの保管が必要です。
ただし、耐久性は高価な製品よりも劣ります。
そのため、耐久性は割り切ってある程度使ったら買い替えるのも方法です。
Q2. 100均のフライパンでも使える?
100均のフライパンも短期間であれば使用可能です。
しかし、スーパーやホームセンターで販売されているフライパンよりも耐久性や安全性には限界があります。
価格が安い分、コーティングが薄く、焦げ付きやすい点がデメリットです。
そのため、100均のフライパンは試しに使う用途や非常時用として有効です。
Q3. 安いフライパンでも焦げ付きにくくする方法は?
安価なフライパンでも、正しい使い方をすれば焦げ付きにくくできます。
以下に、焦げ付きにくくする方法を紹介します。
・中火以下で調理する
・調理を始める前にフライパンを予熱してから油を加える
・調理中には金属製ヘラの使用を避け、シリコン製やナイロン製のヘラを使用する
安いフライパンでは、いかにコーティングが剥がれないように使うかがポイントです。
まとめ
本記事では、安いフライパンの選び方と長持ちさせるコツを紹介しました。
安いフライパンは初期費用が安いかわりに、耐久性や焦げ付きやすさから定期的な買い替えが必要です。
最後になりますが、安くはないもののコストパフォーマンスが高いフライパンを紹介します。
というのも、初期費用が高くても、買い替えがほとんど発生しないフライパンの方がフライパンにかける金額は安くなる場合があります。
クーベルのステンレスフライパンは、実は非常にコストパフォーマンスに優れたフライパンです。
ステンレス素材は頑丈で耐久性に優れており、お手入れなどは普通のフライパンと同じようなお手入れで問題ありません。
加えて、クーベルのフライパンはフライパンの表面がコーティングされていないため、コーティング剥がれを心配する必要がないのです。
ステンレスフライパンの弱点である熱伝導率の低さと重さは、ステンレスとアルミを3層構造にすることで改善しています。
そのため、クーベルのステンレスフライパンは普段のフライパンと同じような使い方ができて、丁寧に扱えば一生使えるフライパンなのです。
安いフライパンを検討するのであれば、長い目でコストがかからないクーベルのステンレスフライパンも検討しましょう。