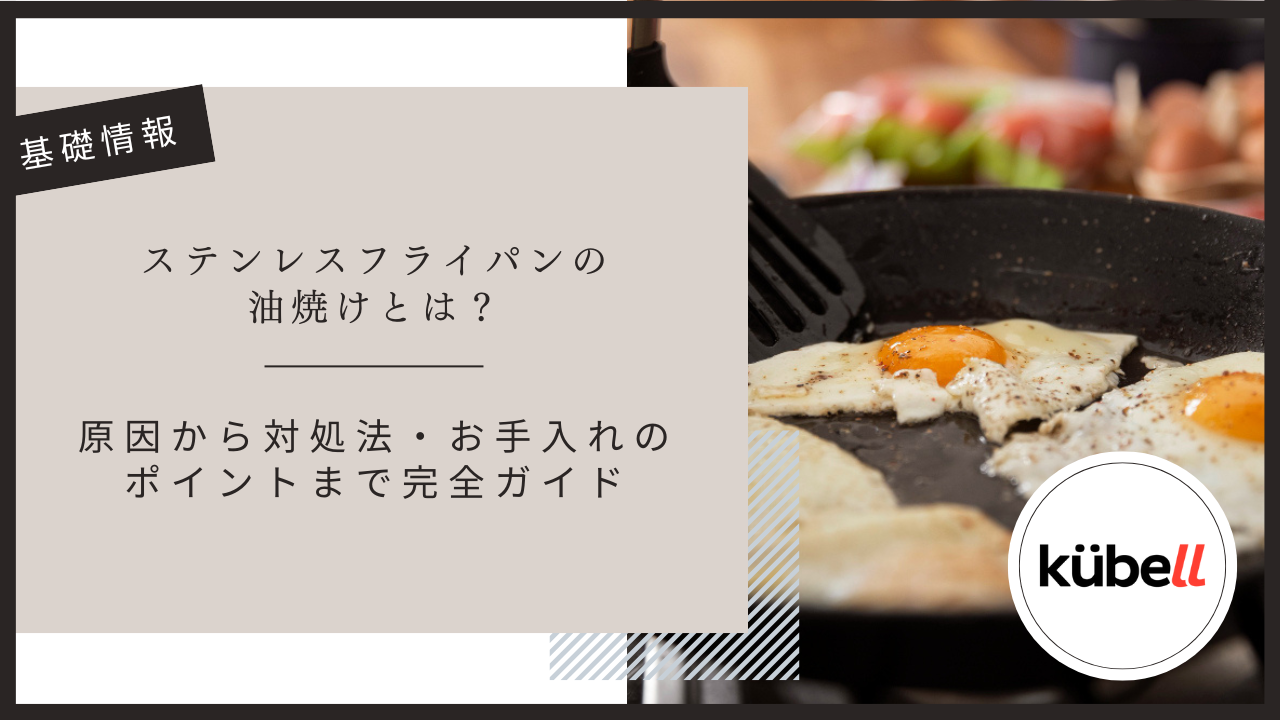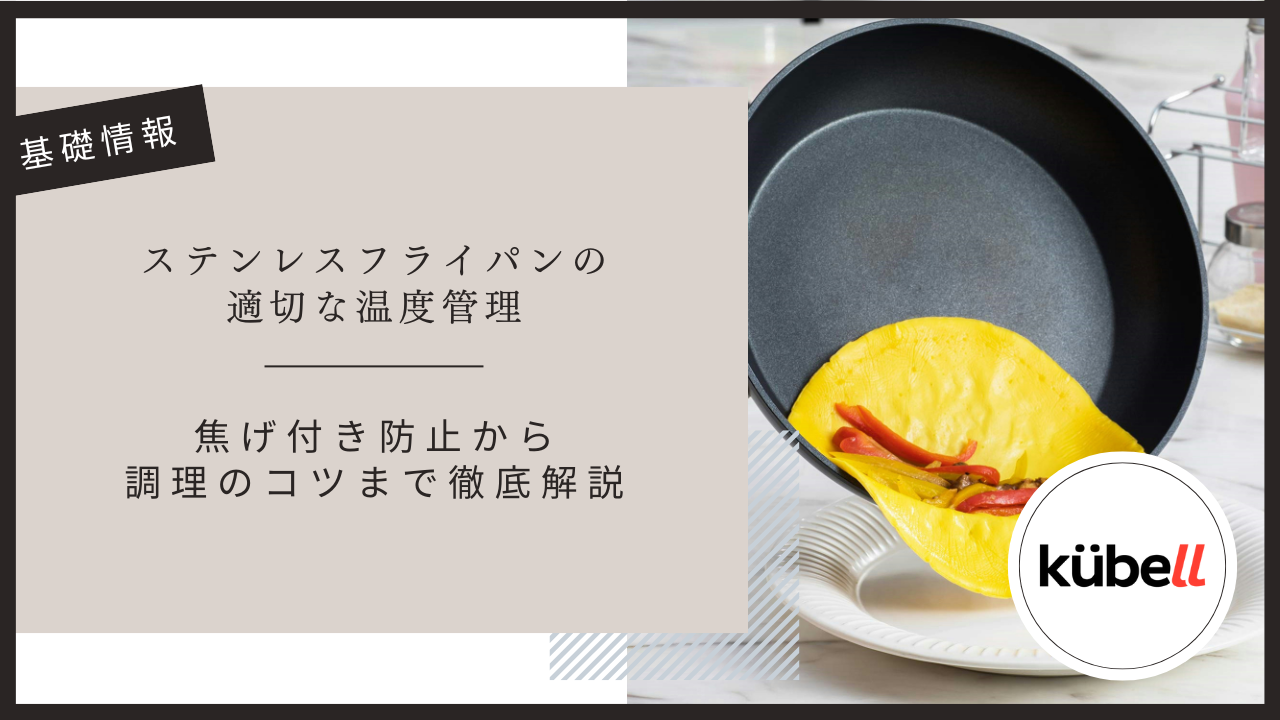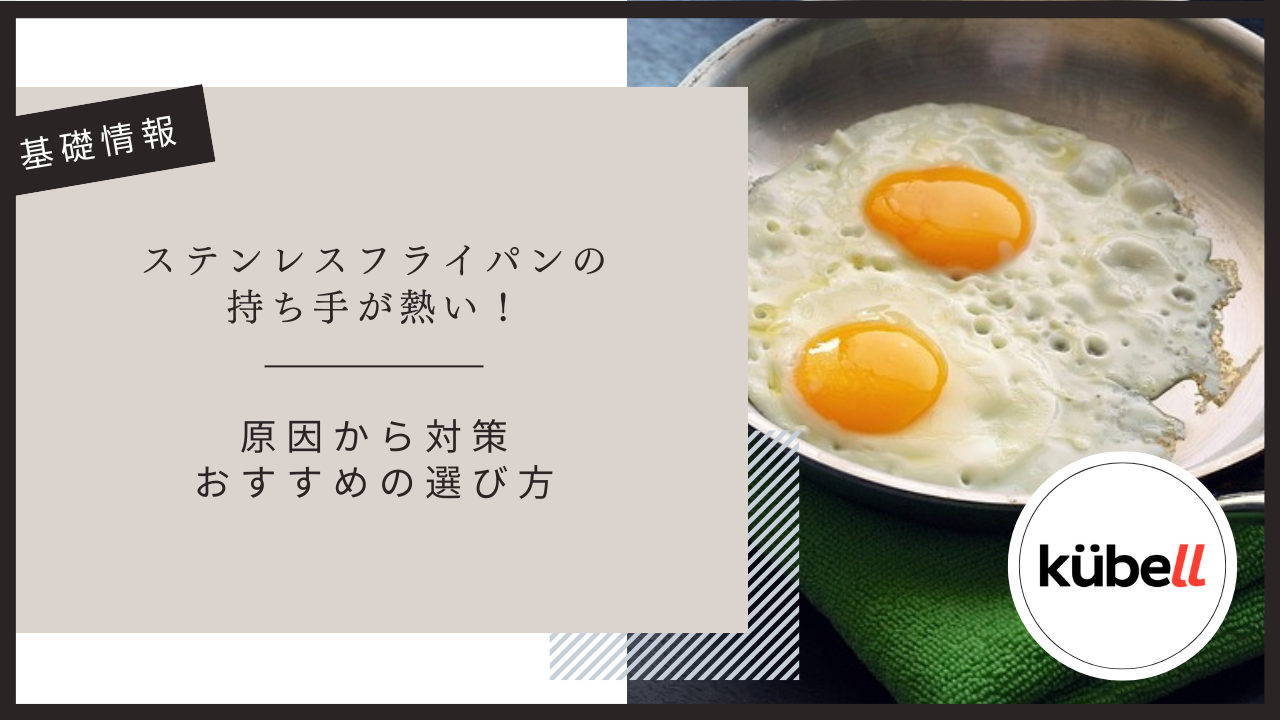
ステンレスフライパンの持ち手が熱い!原因から対策・おすすめの選び方まで徹底解説
「ステンレスフライパンを使ってみたけど、持ち手に布巾が必須で使いづらい」「ステンレスフライパンを使うには持ち手の熱さに耐えないといけないの?」
一般家庭からプロまで幅広く使われているステンレスフライパンは、見た目の良さや熱伝導率の関係で持ち手がステンレスになっている場合があります。そのため、持ち手に布巾を巻いて使うなど工夫をしないと持ち手に触れなくなってしまう場合があります。しかし、ステンレスフライパンの中には、持ち手が熱くならない工夫をしているケースが存在します。本記事では、ステンレスフライパンの持ち手が熱い原因や対策、おすすめ製品を紹介します。
また、ステンレスライパンをご検討の場合はクーベルのステンレスフライパンをご検討ください。ステンレスは温まりにくく冷めにくい素材なので、食材を入れたあとも温度が下がりにくいという特徴を持っています。加えて、予熱を行うことによって油分を多く含む肉や魚などの食材は無油調理を行うことも可能で、余分な油とカロリーを抑えた健康に良いヘルシーな料理が楽しめます。ぜひこの機会に、一生モノのフライパンをお手に取ってみてください。
ステンレスフライパンの持ち手が熱くなる原因
ステンレスフライパンは耐久性や使いやすさから多くの家庭で愛用されていますが、調理中に持ち手が熱くなってしまう場合があります。持ち手が熱くなる主な原因には、フライパンの素材や構造、調理方法などが関係しています。そこで、持ち手が熱くなる原因を紹介します。
熱伝導率とデザインの影響
ステンレスフライパンの持ち手が熱くなる原因の一つは、素材の熱伝導率とデザインです。前提として、ステンレス鋼は鉄などに比べると熱伝導率が低い素材ですが、それでも熱は伝わります。特に、持ち手がフライパン本体と一体型になっているデザインの場合、熱が直接伝わりやすくなります。くわえて、持ち手の形状や厚みによっても熱の伝わり方が変わってきます。薄い持ち手や、本体との接合部が広い設計のフライパンは熱が伝わりやすい傾向です。一方で、持ち手の中が空洞になっているケースや断熱材を使用したデザインであれば、熱が伝わりにくくなっています。
多層構造・単層構造による違い
フライパンの構造も、持ち手の熱さに影響を与える重要な要素です。多層構造と単層構造では、熱の伝わり方に違いがあります。単層構造のステンレスフライパンは、多層構造に比べて熱が直接持ち手に伝わりやすい構造です。一方、多層構造のフライパンは、ステンレスとアルミニウムなど異なる素材を組み合わせて作られています。多層構造では、単層構造に比べて熱が効率よく底面や側面に広がり、持ち手への熱の伝導を抑えます。ただし、多層構造でも完全に熱の遮断はできないため、長時間の調理や高温での使用では持ち手が熱くなる可能性があります。
調理時の火加減とコンロサイズの関係
持ち手の熱さは、調理時の火加減やコンロのサイズにも関係します。強火で調理したり、フライパンよりも大きな火力のコンロを使用したりすると、持ち手が熱くなりやすいです。特に、ガスコンロの炎がフライパンの底面からはみ出して側面に当たった場合、持ち手に熱が伝わりやすくなります。さらには、長時間の調理や高温での調理も、持ち手を熱くする原因となります。持ち手の熱さを軽減するには、適切な火加減を心がけ、フライパンのサイズに合ったコンロを選びましょう。
持ち手の熱さを軽減する選び方・ポイント
ステンレスフライパンを選ぶ際、持ち手の熱さを軽減するためのポイントがいくつかあります。そこで、熱さを軽減する持ち手の選び方を紹介します。
熱くなりにくいハンドル形状・素材
持ち手の形状や素材は、熱の伝わりやすさに大きく影響します。そのため、熱くなりにくいハンドルを選ぶことがポイントです。ハンドル形状としては、持ち手が本体から少し離れた形状がおすすめです。というのも、持ち手が本体から少し離れていれば、直接的な熱伝導を抑えられます。熱くなりにくい素材としては、耐熱性プラスチックを使用したハンドルや木材を選びましょう。プラスチックや木材は熱伝導率が低く、触っても熱くなりにくい特徴があります。ただし、耐熱系の持ち手はオーブン調理には適さない場合があるので、使用目的に応じた選択が大切です。
樹脂ハンドル・シリコンカバーのメリット
樹脂ハンドルは、耐熱性プラスチックや木材などと同じく熱が直接伝わりにくくなっています。樹脂ハンドルは滑りづらく、加えて握りやすい形状に設計されているため使い勝手も良好です。シリコンカバーは、既存のステンレスハンドルに後付けで装着できるアイテムです。耐熱性が高く、柔らかい触り心地が特徴です。金属製であっても、シリコンカバーの使用でハンドルの熱さが大幅に軽減できます。ただし、これらの素材も長時間の高温調理では熱くなる可能性があるので、注意が必要です。
長めの持ち手・空洞構造での熱対策
持ち手の長さや構造も、熱対策として重要なポイントです。長めの持ち手や空洞構造を採用したフライパンであれば、熱さを軽減できる可能性があります。長めの持ち手は、本体からの距離が取れるため、熱が伝わりにくくなります。特に、持ち手の根元から先端にかけて徐々に細くなるデザインのものは、熱の伝導を抑える効果があります。ただし、長い持ち手は収納時に場所を取るデメリットもあるので、自分の使用環境に合わせた選択が大切です。構造としては、空洞構造の持ち手も断熱効果にはおすすめです。持ち手の内部に空気層を作り、フライパン本体からの熱を抑えます。
持ち手が熱いときの対策アイテム・工夫
ステンレスフライパンの持ち手が熱くなってしまった場合でも、いくつかの対策アイテムや工夫で問題を解決できます。熱い持ち手を使い続けた場合、調理中の不快感や火傷のリスクがあるため対策は必須です。
鍋つかみ・ミトンの活用
鍋つかみやミトンは、熱い持ち手から手を守る方法です。鍋つかみは、コンパクトで使いやすく、片手で持ち上げる際に便利で必要な時だけ使用できるので効率的です。様々な素材やデザインのものがあり、キッチンの雰囲気に合わせて選べるのも魅力です。手全体を覆うミトンは、鍋つかみよりも広い面積を保護できるので、大きなフライパンや重い鍋を扱う際に適しています。さらには両手用のミトンを使えば、より安定してフライパンを持ち運べます。ただし、水分を含むと熱が伝わりやすくなるため、濡れた状態での使用は避けましょう。
シリコンカバー・ハンドルカバーを使う
シリコンカバーやハンドルカバーは、既存のフライパンの持ち手に装着して使用する便利なアイテムです。シリコン素材は耐熱性が高く、柔らかい触り心地も特徴です。ハンドルカバーには、シリコン以外にも布製やネオプレン製などがあります。好みの素材や色を選べるので、キッチンの雰囲気に合わせやすいのも魅力です。カバーを装着しておくと、直接金属に触れることなくフライパンを扱えるようになります。また、滑りにくい性質もあるので、安全性が向上します。ただし、これらのカバーも長時間の高温調理では熱くなる可能性があるので、注意が必要です。くわえて、オーブン調理の際は必ず取り外すようにしましょう。
フライパンを小まめに持ち上げない調理方法
調理方法の工夫でも、持ち手が熱くなるのを防げます。特に、フライパンを小まめに持ち上げない調理方法を心がけることが効果的です。例えば、炒め物をする際は、フライパンを持ち上げて食材を返すのではなく、菜箸やフライ返しを使って食材を動かします。また、煮込み料理などでは、蓋をして弱火で蒸し焼きにする調理もおすすめです。ステンレスは保温性が高いため、長時間調理の場合は途中で火を止めて持ち手を冷ますのも1つの方法です。とはいえ、料理によってはフライパンを持ち上げる必要があるため、状況に応じて適切な方法を選びましょう。
よくあるトラブルシューティング
ステンレスフライパンを使用していると、持ち手に関連するさまざまなトラブルに遭遇します。持ち手にも注意を払えれば、フライパンのメンテナンスが容易になり、良好な状態を長期間キープできます。そこで、よくあるトラブルとその解決方法について説明します。
ハンドルのリベットや接合部の焼き付きを軽減する
ハンドルのリベット(接合部の金属ピン)や接合部に食材が焼き付いてしまうケースがあります。焼き付きを防ぐには、調理後にすぐに洗うのが重要です。特に、リベット周辺は食材が溜まりやすいので、しっかり洗いましょう。洗い方は柔らかいスポンジを使い、必要に応じて食器用洗剤を使用します。焼き付きで汚れが取れづらくなった場合は、お湯に浸して柔らかくしてから洗うと効果的です。汚れが取れない場合は、自然素材の重曹やクエン酸、研磨剤を使った洗浄も有効です。ただし、強い研磨剤はフライパン表面を傷つける可能性があるので説明書を確認した上で使いましょう。
ハンドルがグラつく・劣化した場合の対応
長期間の使用や不適切な扱いにより、ハンドルがグラついたり劣化したりするケースがあります。グラつきの原因がネジ緩みの場合は、ドライバーの締め直しを行います。ただし、無理に締めすぎると持ち手が破損してしまう場合があるため、締めすぎには注意が必要です。使用年数や熱による影響で、樹脂製ハンドルの劣化(ひび割れや変色など)が発生する場合があります。軽度の場合は使用を続けられますが、経年劣化であれば安全に使用するためにも持ち手もしくはフライパン自体の交換をおすすめします。製品によっては交換用のハンドルを販売している場合もあるので、持ち手の交換可否について製造元に確認しましょう。
熱で変色・焦げ付きが発生したときのケア
ステンレスフライパンの持ち手が熱によって変色する場合や、焦げ付きが発生するケースがあります。変色は、主に高温での調理や長時間の使用によって起こります。特にステンレス製の持ち手では、熱による酸化が原因で青や茶色の変色が見られるケースがあります。変色がひどい場合は、専用のステンレスクリーナーを使用すると効果的です。クリーナーを柔らかい布に取り、変色部分を磨いて元の輝きを取り戻します。焦げ付きは、調理中に食材や油が持ち手に付着し、そのまま高温で焼き付けると発生するため、しっかり洗うのが重要です。焦げ付きがひどい場合は、持ち手をお湯に浸して柔らかくするか、重曹やクエン酸などで洗いましょう。例えば、重曹と水を混ぜてペースト状にし、焦げ付き部分に塗ってしばらく置いてから磨く方法があります。
クーベルのステンレスフライパンはブナ材使用で調理時に熱くならない
クーベルのステンレスフライパンでは、持ち手にはブナ材を使用しています。加えて持ち手の場所がフライパンから少し離れているため、布巾やカバーなどを使わずに持ち手をそのまま持って調理できます。ブナ材は北欧家具でよく使われており、熱くならないだけでなく、見た目もおしゃれです。クーベルのステンレスフライパンは、3層構造のステンレス素材で熱伝導率と保温性を両立させています。フライパンの表面は無加工なため、丁寧に使えば一生涯使えるフライパンです。さらに、経年劣化が発生しやすい持ち手は、交換パーツが販売されているため交換しながら使えます。良い製品を長く愛用する人や、ものを大切にしたい人、ぜひクーベルのステンレスフライパンを検討しましょう。
よくある質問(Q&A)
ステンレスフライパンの持ち手に関するよくある質問について、インターネットを中心に調査しました。ステンレスフライパンの持ち手が気になる人は、ぜひ回答を参考にしてください。
Q1. 持ち手の樹脂やシリコンは耐久性がある?
樹脂やシリコン製の持ち手は耐熱性と耐久性に優れていますが、使用環境によって劣化してしまうケースがあります。樹脂やシリコン製素材は一般的には200℃前後まで耐えられるため、家庭での調理には問題ありません。劣化してしまうケースとしては、高温で長時間調理を続けた場合です。例えば、オーブン調理や直火調理では樹脂やシリコン製ハンドルが変形したりひび割れたりする可能性があります。持ち手の樹脂やシリコンの耐久性を保つためには、定期的な清掃と適切な使用方法が重要です。加えてメーカーによって耐熱性能が異なるため、購入時には仕様を確認しましょう。
Q2. 焚き火や直火調理でハンドルが熱くなるのを防げる?
焚き火や直火調理では、高温の炎がフライパン全体に直接当たるため持ち手は熱くなりがちです。防ぐ方法としては、焚き火用やキャンプ用として設計されたフライパンを選ぶ方法があります。焚き火用やキャンプ用のフライパンは、断熱性の高い素材や空洞構造を採用しているため、高温環境でも持ち手が熱くなりにくい設計です。加えて、焚き火で使用する場合は、フライパンの熱さ以外にも火傷などの防止のために耐熱グローブの使用がおすすめです。持ち手部分にシリコンカバーなどの断熱アイテムの使用も効果的ですが、高温環境ではカバー自体も熱くなる可能性があるため注意してください。
Q3. 熱伝導率の低いステンレス素材はある?
ステンレス素材は、鉄素材などに比べて熱伝導率が低く、ステンレス素材の種類によって熱伝導率や耐久性が異なります。ただし、どんな種類のステンレスでも完全に熱伝導率を抑えることはできません。断熱性を考えるのであれば、多層構造(アルミニウムや銅などとの組み合わせ)で断熱性能を高めたフライパンがおすすめです。また、製品によっては、特殊加工で持ち手への熱伝導率を抑える設計のフライパンもあります。
Q4. オーブン調理時は持ち手カバーを使用してもいい?
オーブン調理時は、持ち手カバーの使用はおすすめできません。高温になるオーブン環境ではシリコンの耐熱温度を超えてしまい、溶けたり変形したりする可能性があります。ただし、オーブン対応のハンドルカバーも販売されているので、オーブンで持ち手カバーを使いたい場合は検討しましょう。
Q5. 長い持ち手の方が絶対に熱くなりにくい?
長い持ち手は本体から距離が取れるため、短い持ち手よりも熱くなりにくいのは間違いありません。ただし、絶対に熱くなりにくいかどうかは、長さに加えて設計や素材も重要な要素です。例えば、本体との接合部が広いデザインであれば、長さに関係なく熱伝導率が高まります。また、中空構造や断熱材入りの設計であれば持ち手が短めでも断熱性が発揮できます。そのため、自分の調理スタイルはもちろんのこと、キッチンの広さや収納スペースなども考えながら選びましょう。
まとめ
本記事では、ステンレスフライパンの持ち手の熱さについて紹介しました。デザインが気に入って購入したものの、持ち手が熱くて結局使わなくなった、となってしまっては本末転倒です。家庭用であれば熱くなりづらいハンドルがおすすめですが、カバーを使う方法やフライパンを持ち上げないなど持ち手を触らない方法もぜひ試してみてください。様々な方法で持ち手の熱さが軽減できるため、自分に合った方法で持ち手の熱さを対策しましょう。