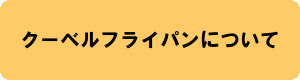「大きいフライパンって便利なの?」
「サイズ別のメリットとデメリットが知りたい」
フライパンを購入しようと考えているものの、どのサイズを購入すれば良いのか決められないという人は少なくないでしょう。それぞれのサイズにはメリットとデメリットがあるので、事前に確認しておくとスムーズに決められます。
今回は、大きいサイズのフライパンの選び方と活用術を紹介します。サイズ別のメリットとデメリットも合わせて紹介しているので参考にしてください。
また、ステンレスライパンをご検討の場合はクーベルのステンレスフライパンをご検討ください。
ステンレスは温まりにくく冷めにくい素材なので、食材を入れたあとも温度が下がりにくいという特徴を持っています。加えて、予熱を行うことによって油分を多く含む肉や魚などの食材は無油調理を行うことも可能で、余分な油とカロリーを抑えた健康に良いヘルシーな料理が楽しめます。
ぜひこの機会に、一生モノのフライパンをお手に取ってみてください。
大きいフライパンが求められる理由
近年、大きいフライパンの需要が高まっている背景には、ライフスタイルの多様化があります。共働き世帯の増加により、食事の準備や作り置きを効率的に行いたいというニーズが強まり、一度に多くの量を調理できるフライパンが非常に重宝されているといえるでしょう。
また、家族の人数が多い家庭や、ホームパーティー・アウトドアなどのシーンでも活躍します。また、大きいフライパンはホットプレートの代わりとして使える手軽さも魅力だといえるでしょう。
調理の幅が広がり、時短にもつながる便利なアイテムとして支持されています。
大きいフライパンのメリット・デメリット
ここでは大きいフライパンのメリットとデメリットを紹介します。メリットとデメリットを把握しておくことで、よりフライパン購入の検討が進めやすくなるでしょう。
以下の内容を確認して、購入するフライパンのサイズを決める際の参考にしてください。
-
メリット|一度にたくさん調理できる利便性
-
デメリット|収納や重量、扱いやすさの問題
メリット|一度にたくさん調理できる利便性
大きいフライパンの最大のメリットは、一度にたくさんの食材を調理できるという点です。家族分の食事や作り置きや弁当のおかずなどを効率よく準備でき、時短にもつながります。また、フライパンに入れた具材同士が重ならず、炒め物や焼き物がムラなく仕上がるのも魅力だといえるでしょう。
さらに、大きいフライパンはホットプレート代わりとして餃子やお好み焼きをそのままテーブルで仕上げるといった使い方もできます。大きいフライパンは料理の自由度が広がり、調理ストレスを軽減してくれる優秀アイテムです。
デメリット|収納や重量、扱いやすさの問題
大きいフライパンには、収納場所を取る・重くて扱いにくいというデメリットがあります。特に30cm以上のサイズになると、キッチンの収納棚やシンクでの洗浄スペースに困ることも少なくありません。
また、調理中に片手で持ち上げるのが難しいため、腕や手首への負担が増える可能性もあります。フライパンの扱いに慣れていないという人は、扱いに苦戦してしまう可能性があります。
家庭のコンロのサイズによっては加熱ムラが起きやすく、使いこなすにはある程度の工夫が必要になるでしょう。利便性とのバランスを見極めることが大切です。
大きいフライパンのサイズ選びのポイント
ここでは大きいフライパンのサイズ選びのポイントをまとめています。以下の内容を参考にすると、どのサイズのフライパンを購入するべきなのか判断しやすくなるでしょう。
-
26cm・28cm・30cm・32cm以上のサイズ比較
-
用途別|何人分の料理に適している?
-
重さと扱いやすさのバランス
26cm・28cm・30cm・32cm以上のサイズ比較
フライパンのサイズは調理スタイルに大きく影響します。26cmは一人暮らしや2人分に最適で、収納や洗浄が楽になる傾向があります。
28cmは3〜4人家庭のメインサイズとしてバランスが良く、炒め物や焼き物に最適だといえるでしょう。30cmは作り置きや4人以上の食事作りに最適で、具材を重ねずに調理できます。
32cm以上はパーティー料理や大量調理向きですが、コンロや収納スペースに制限がある場合は注意しなければなりません。それぞれの生活スタイルや用途に合った選び方が大切です。
用途別|何人分の料理に適している?
26cmのフライパンは1〜2人分の調理にちょうど良く、少量の炒め物や卵料理に最適です。28cmは2〜3人分のメイン料理や副菜を同時に作れるバランス型だといえるでしょう。
30cmになると3〜5人分の調理が可能で、食べ盛りの子どもがいる家庭や作り置きに向いています。32cm以上は5人以上の家族や、大皿料理・イベント料理にも対応できる大容量サイズです。
人数や料理の種類に合わせてフライパンのサイズを選ぶことで、毎日の食事作りがより快適になります。
重さと扱いやすさのバランス
フライパンはサイズが大きくなるほど重さが増してしまう傾向があるので、扱いやすさとのバランスが非常に重要になります。26cmは軽くて片手でも扱いやすく、洗いやすい点が魅力だといえるでしょう。
28cmのフライパンはやや重くなるものの、多用途に使えるサイズ感です。30cm以上になると両手で持ち上げる必要があり、腕力や収納スペースも考慮すべきポイントになるでしょう。
フライパンの材質によっても重さは異なり、アルミは軽く、鉄やステンレスは重くなるポイントになります。
素材別|大きいフライパンの特徴と選び方
素材別で大きいフライパンの特徴と選び方を紹介します。フライパンのサイズはもちろん、素材別の特徴を確認しておくことで、自分に合っているフライパンの購入検討を進めやすくなるでしょう。
以下の内容を参考にして、フライパンの購入検討の参考にしてください。
-
フッ素樹脂コーティング(軽量でこびりつかない)
-
鉄・鋳鉄(高火力・耐久性抜群)
-
ステンレス(ムラなく均等に火が通る)
-
アルミ・多層構造(熱伝導が良く軽量)
フッ素樹脂コーティング(軽量でこびりつかない)
フッ素樹脂コーティングのフライパンは、軽量で扱いやすく、食材がこびりつきにくいのが特徴です。油を少量に抑えられるため、ヘルシー志向の調理にも適しています。
フッ素樹脂コーティングのフライパンは焦げ付きにくく、洗い物も簡単なので、忙しい日常にも最適だといえるでしょう。ただし、フッ素樹脂コーティングのフライパンは高温調理や金属製のヘラに弱く、コーティングが傷むと性能が落ちる点には注意が必要になります。
耐久性はやや低めですが、手軽に使える万能選手として人気の高いタイプです。
鉄・鋳鉄(高火力・耐久性抜群)
鉄や鋳鉄のフライパンは、熱に非常に強く、高火力調理に最適です。鉄や鋳鉄のフライパンは、使い込むほど油がなじんでフライパンが育っていく楽しさがあり、プロの料理人にも愛用者が多い素材です。
ステーキやチャーハンなど、香ばしさを出したい料理に最適で、非常に丈夫で長持ちします。しかし、鉄や鋳鉄のフライパンは、他の素材のフライパンよりも錆びやすいため手入れに少し手間がかかります。鉄や鋳鉄のフライパンは、しっかりとメンテナンスできる人向けの、使い応えのある本格派フライパンです。
ステンレス(ムラなく均等に火が通る)
ステンレス製のフライパンは、熱をじっくり伝えてくれるため、焼きムラが出にくく素材の旨味を引き出す調理に適しています。ステンレス製のフライパンは酸やアルカリにも強く、長く美しい状態を保てるのも魅力だといえるでしょう。
ステンレス製のフライパンは、炒め物よりも焼き付けてから煮込むなど、じっくり調理する料理に向いています。ただし、熱伝導はやや劣るため、アルミなどと組み合わせた多層構造が主流だといえるでしょう。
重めでこびりつきやすいので、使いこなすには慣れが必要になるかもしれません。
アルミ・多層構造(熱伝導が良く軽量)
アルミ製のフライパンは、熱伝導が非常に良く、軽量で扱いやすいため、日常使いにぴったりです。料理に慣れていない人でも扱いやすい素材のフライパンだといえるでしょう。
火の通りが早く、時短調理が可能で、取り回しやすさも抜群です。ただし単層のアルミは焦げ付きやすく、変形しやすいため、耐久性を求めるならステンレスとの多層構造やコーティング加工を選ぶのが良いでしょう。
IH非対応の製品もあるので、購入時は熱源への対応を要確認。使いやすさと調理効率を両立させたい人に最適な素材です。
大きいフライパンの使いこなし術
大きいフライパンの使いこなし術を紹介します。使いこなし方を知っておくことで、よりフライパンを使いこなせるようになるでしょう。
フライパンの扱いに慣れていない人はもちろん、フライパンに慣れている人も以下を確認してください。
-
炒め物・焼き物・揚げ物に最適な調理テクニック
-
大人数向けの時短調理のポイント
-
重さを感じさせない調理法
炒め物・焼き物・揚げ物に最適な調理テクニック
大きいフライパンでの炒め物は、具材を重ねず広げるのがコツだといえるでしょう。強火で一気に炒めることでシャキッと仕上がります。
焼き物はフライパン全体をしっかり予熱し、油をまんべんなく広げてから食材を投入すると、ムラなく焼き色がつきます。揚げ物には底が深めの大きいフライパンを使うと、油はねを防ぎつつ多めに揚げられて効率良く調理を進められるでしょう。
フライパンだけでなく温度計も用意すると、さらに安定します。調理ごとに火加減と配置を意識するのがポイントです。
大人数向けの時短調理のポイント
大きいフライパンで大人数分を効率よく調理するには、下ごしらえをしっかり行い、具材ごとに火の通りやすさを把握することが欠かせません。大きいフライパンを活かして具材を重ならないように並べることで、加熱ムラを防ぎ時短につながるでしょう。
また、炒め・煮込みの順で一つの大きいフライパンで完結するワンパン調理もおすすめです。工程を省けるだけでなく、時短にもつながるでしょう。調理中はフライパン全体を活用し、空いたスペースで同時進行するなど工夫次第で驚くほど効率がアップします。
重さを感じさせない調理法
大きいフライパンの重さが気になる場合は、持ち上げずに調理する工夫がポイントです。調理台にフライパンをしっかり置いたまま具材を返すには、シリコンスパチュラやトングなどを活用するのが良いでしょう。
食材をフライパンから容器へ移す際も、フライパンごと傾けるのではなく器を近づけてすくい取るようにすると腕や手への負担が減ります。また、片手での持ち上げを避け、両手を使って安定させることで手首の疲れを防げるでしょう。大きなフライパンを購入する場合には、重さを感じさせない調理法を心がけて工夫してください。
よくある質問(FAQ)
ここでは、大きいフライパンの選び方と活用術に関するよくある質問と回答を紹介します。疑問点や不明な点が解消する可能性があるので、事前に確認しておくのが良いでしょう。
以下の内容を参考にして、大きいフライパンの選び方と活用術に関する質問と回答を確認してください。
-
Q1. 大きいフライパンは重くて扱いにくくない?
-
Q2. 何人分の料理に適しているサイズ?
-
Q3. 大きいフライパンの熱ムラを防ぐ方法は?
Q1. 大きいフライパンは重くて扱いにくくない?
30cm以上の大きいフライパンは重くなりがちですが、使い方次第で扱いやすさは大きく変わります。大きいフライパンを調理中に無理に持ち上げず、トングやヘラで具材を動かすことで手首への負担を軽減可能です。
また、取っ手がしっかりしていてバランスの良い製品を選ぶと、安定感が増して扱いやすくなるでしょう。大きいフライパンの収納や洗浄時にシンク内で安定させながら行うなど工夫次第で扱いやすさは向上します。
自分の体力や使い方に合った重さのフライパンを選ぶのがポイントです。
Q2. 何人分の料理に適しているサイズ?
フライパンのサイズを選ぶ際に、人数に応じて選ぶと調理効率がアップします。26cmは1〜2人分、28cmは2〜3人分に最適で、コンパクトでありつつも汎用性があります。
30cmになると3〜5人分の食事に対応でき、作り置きにも便利だといえるでしょう。32cm以上は5人以上やイベント、パーティー料理向きで大皿料理を一気に調理したいときに活躍します。
自分や作る相手の食べる量、人数や調理頻度も考慮して、自分の生活スタイルに合ったフライパンのサイズを選ぶのが大切です。
Q3. 大きいフライパンの熱ムラを防ぐ方法は?
大きいフライパンはサイズゆえにコンロの火が全体に届きにくく、熱ムラが出やすい傾向があります。これを防ぐには、まずフライパン全体をしっかり予熱することが重要になるでしょう。
弱火から中火で時間をかけて均一に温めると、フライパンの温度ムラが出にくくなります。また、IH対応の多層構造や底が厚めのフライパンを選ぶことで熱が均等に広がりやすくなります。
フライパンで炒め物をする際には具材をこまめに動かし、空いている部分も活用することで均一な加熱が可能になるでしょう。
まとめ
大きいフライパンは選び方と活用術を知ることで、より便利に使えます。フライパンのサイズ別のメリットやデメリットを確認した上で、自分に最適なものを選択するのが良いでしょう。
kübell (クーベル)のステンレスフライパンは、質が高い金属のみを使用しているので、手入れ次第で半永久的に使い続けられます。こびりつかず使い勝手が良いステンレスフライパンを探しているという場合には、kübell (クーベル)のステンレスフライパンを候補に入れて検討を進めて下さい。