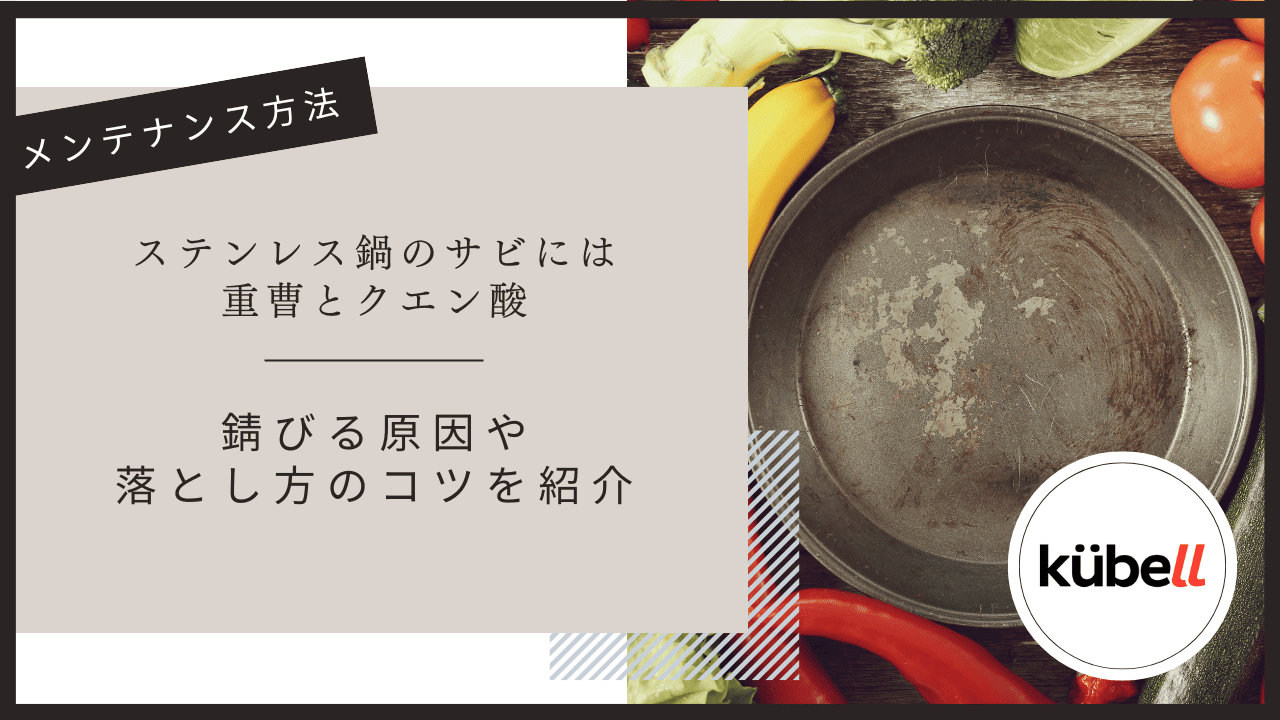
ステンレス鍋のサビには重曹とクエン酸!錆びる原因や落とし方のコツを紹介
ステンレスと言えば丈夫で錆びにくい材質として有名です。そもそもステンレスという名前は英語でサビを意味するStainと否定の意味を含むlessを合わせた造語であり、その事からもなかなかサビない金属であるということが分かるかと思います。
しかし、そんなステンレスでも実は錆びてしまうことがあるんです。この記事では、ステンレス鍋の性質を解説しながら、錆びる原因やサビを落とす方法について詳しく紹介していきます。
また、ずっと使い続けたくなる一生モノのフライパンをご検討の場合はクーベルのステンレスフライパンをご検討ください。
ステンレスは温まりにくく冷めにくい素材なので、食材を入れたあとも温度が下がりにくいという特徴を持っています。加えて、予熱を行うことによって油分を多く含む肉や魚などの食材は無油調理を行うことも可能で、余分な油とカロリーを抑えた健康に良いヘルシーな料理が楽しめます。
ぜひこの機会に、一生モノのフライパンをお手に取ってみてください。
ステンレスはなぜ錆びにくい?

ステンレスが錆びにくい理由は、金属自体が空気に含まれる酸素に触れることで酸化し、保護(酸化)皮膜を形成するためです。
つまり、酸素に触れるだけで、錆びを防ぐバリアが張られるようなイメージです。さらに、クーベルのステンレスフライパンは調理面にニッケルが含まれるSUS304というステンレスを使っており、こちらは一般のステンレスよりも強固な保護皮膜が形成されるため、より一層錆びにくくなっています。
また、酸化被膜は仮になんらかの原因で傷がついたとしても、すぐに形成される特徴があります。そのため、銅製の鍋のように傷が原因で中毒を引き起こしてしまうといった危険性もなく、半永久的にサビを防ぐことが可能です。
上記の通り、非常に錆びにくい特徴を持つステンレス鍋ですが、場合のよっては錆びてしまうことはあるのでしょうか?
ステンレスが錆びる原因は?
 結論から言うと、ステンレス素材は他の素材や物質の影響を受けて錆びることがあります。ここからは、ステンレスが錆びる原因について、具体的に説明します。
結論から言うと、ステンレス素材は他の素材や物質の影響を受けて錆びることがあります。ここからは、ステンレスが錆びる原因について、具体的に説明します。
もらいサビとは?
まずはもらいサビという現象についてです。ステンレス鍋の上に鉄などの錆びやすい金属を直接触れるように保管してしまうと、別の金属のサビが移ることで錆びてしまうのです。そのため、保管する際には鉄やアルミなどの素材のフライパンに触れないようにしましょう。
サビの原因
他の原因としては、ステンレス鍋に汚れを付けた状態で放置してしまったり、水分が多くあるような場所に保管してしまった、というものも考えられます。調理を終えたあと、食材には油分や酸など、金属の劣化を引き起こす原因となる物質が多く含まれています。もちろん、使用後すぐに洗わなくてはいけないということはありませんし、それほど神経質になる必要はありません。
ただし、使用後に数日間放置するといったことはお控えください。それに加え、水が頻繁にこぼれてしまうような場所や、海の近くで潮風が直接当たるような場所での保管も避けましょう。保管方法については以前にも記事を書いているので、ご参照ください。
https://ku-bell.com/blogs/blog/storage
ステンレスが錆びてしまった場合の対処法は?

軽度のものであれば、金たわしやスチールウールなどで洗うことで除去できます。もしそれでも落ちない場合、黒錆には重曹を直接かけてこすることで対処しましょう。赤茶色い錆には、クエン酸を水で薄めて磨くことで落としやすくなります。また、クレンザーなどをご使用いただくことも可能です。穴が空くほどの状態になってしまったら、修理が必要となります。
ここからは、重曹とクエン酸それぞれの使い方について、詳しく紹介していきます。また、錆がひどい場合には重曹とクエン酸を組み合わせて使うと効果的です。こちらもあわせて解説します。
重曹を使う場合
重曹を使うと、ステンレスの鍋の黒いサビを綺麗に落とすことが可能です。手軽にサビを落とすことができるため、ぜひ方法について知っておきましょう。重曹でサビを落とす場合の手順は、以下の通りです。
- 鍋を水で洗い、軽い汚れを落とす
- 粉末の重曹をサビの箇所に直接かけ、水で濡らしたメラミンスポンジでこする
- サビが浮いてきたら水で洗い流し、乾いた布で水気を拭き取る
重曹は強い研磨作用がある点が特徴なので、ステンレス鍋のサビをしっかりと取ることができます。
クエン酸を使う場合
サビはアルカリ性のため、酸性のクエン酸により中和反応が起こり、落ちやすくなります。特に赤茶色の錆びにはクエン酸が非常に有効です。クエン酸でサビを落とす場合の手順は、以下の通りです。
- 洗面器などにぬるま湯を張る
- ぬるま湯100mlに対し小さじ1/2のクエン酸を溶かし、クエン酸液を作る
- クエン酸液をキッチンペーパーや雑巾に含ませ、サビの箇所にのせて30分ほどつけ置きする
- 雑巾またはキッチンペーパーを取り除きしっかりと水洗いする
クエン酸は100円ショップでも簡単に手に入るため、手軽に試せておすすめです。
重曹とクエン酸を使う場合
サビがあまりにひどい場合は、重曹とクエン酸を組み合わせて使うと効果的です。以下で、重曹とクエン酸を組み合わせてサビを取り除く手順を確認してみてください。
- 洗面器などの容器に、水100mlあたり小さじ1/2のクエン酸を溶かしてクエン酸液を作る
- サビの箇所に、粉末の重曹をふりかける
- ふりかけた重曹の上から、クエン酸液を少しかける
- 泡が出て汚れが浮いてきたら、メラミンスポンジでこする
- 水で洗い流し、乾いた布で水気を拭き取る
重曹だけ・クエン酸だけではサビが取れない場合、上記の方法を試してみると良いでしょう。
ステンレスのサビを落とす際のポイント

ステンレスのサビの落とし方を誤ると、かえってサビを増やしたり鍋を傷つけてしまったりする可能性もあるでしょう。ここからはステンレスのサビを落とす際のポイントについて、詳しく説明していきます。ステンレスのサビを落とす前にチェックしておき、大切な鍋や調理器具を傷つけないように注意しましょう。
強くこすり過ぎないように気をつけよう
ステンレスのサビを落とす際には、やさしく丁寧に行うのが大切です。ステンレスは傷がついた場所から、錆びができやすい特徴があります。さらに別の場所で、もらい錆びが起こりやすくなってしまうでしょう。汚れが落ちないからといって、強くゴシゴシ洗うのはおすすめできません。
長時間のつけ置きは避けよう
重曹やクエン酸をサビにつけた後、長時間放置し過ぎると鍋を傷めてしまう可能性があります。低刺激の重曹やクエン酸を使っていたとしても、たとえば数時間も放置すると、ステンレスの素材にダメージを与える原因につながってしまいます。そのため、つけ置きする時間の目安として、およそ30分から1時間までで止めるのがおすすめです。
クエン酸を使う場合は、鉄製の物を遠さげよう
クエン酸は、鉄などの金属と非常に相性が悪い性質があります。鉄製の鍋や包丁の近くでクエン酸を使うと、サビを増加させる原因につながってしまう可能性があるでしょう。そのため、クエン酸を使う場合は、鉄製の物を遠ざけておくべきです。
まとめ
ここまで、ステンレスがなぜ錆びにくいのかという話から、錆びてしまう原因・解決方法について説明しました。みなさんも、正しい知識を持つことで、ステンレスフライパンをより便利にご使用いただければと思います。
特に、当社クーベルのフライパンは調理面にフッ素樹脂加工を行っていないため、一生愛用できる製品です。筆者もクーベルのステンレスフライパンを使ってずいぶん時間が経ちましたが、全く錆びる気配もなく、驚いています。錆びにくく、できるだけ長く愛用できるステンレスフライパンをお探しの方は、当社の製品をチェックしてみてはいかがでしょうか。
当社自慢のステンレスフライパンは以下のボタンから確認できますので、興味がある方は確認してみてください。














