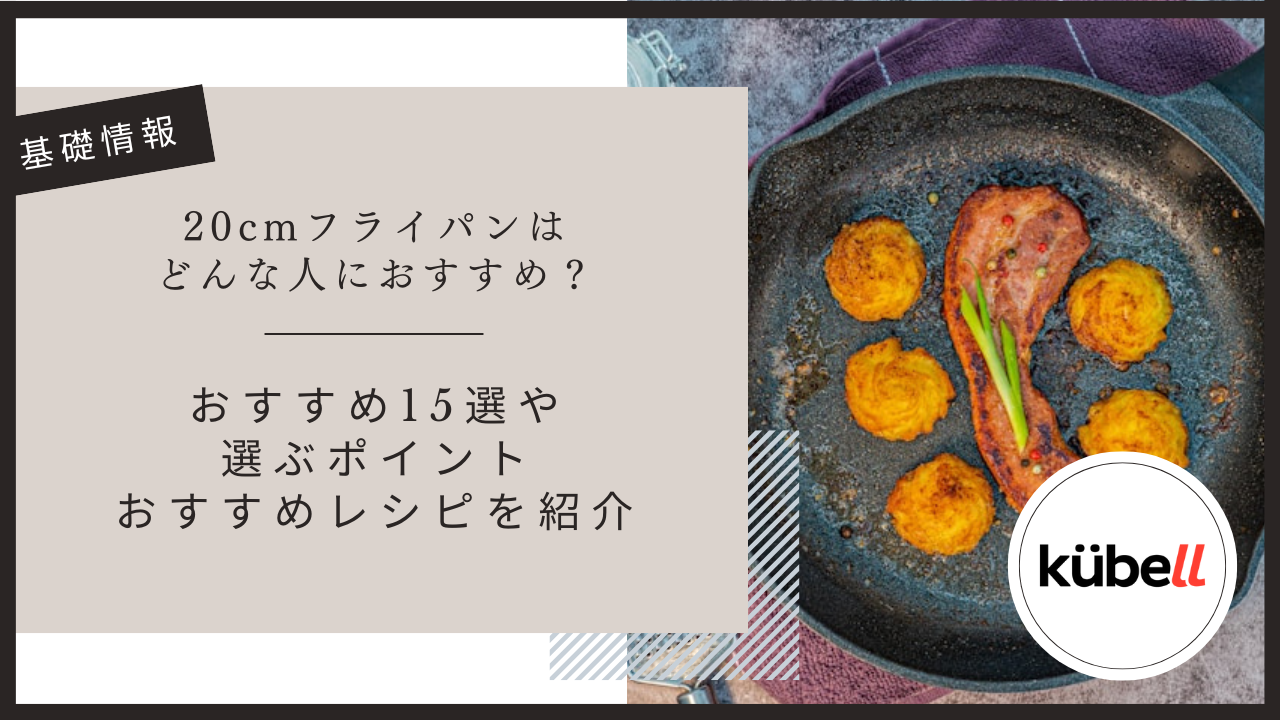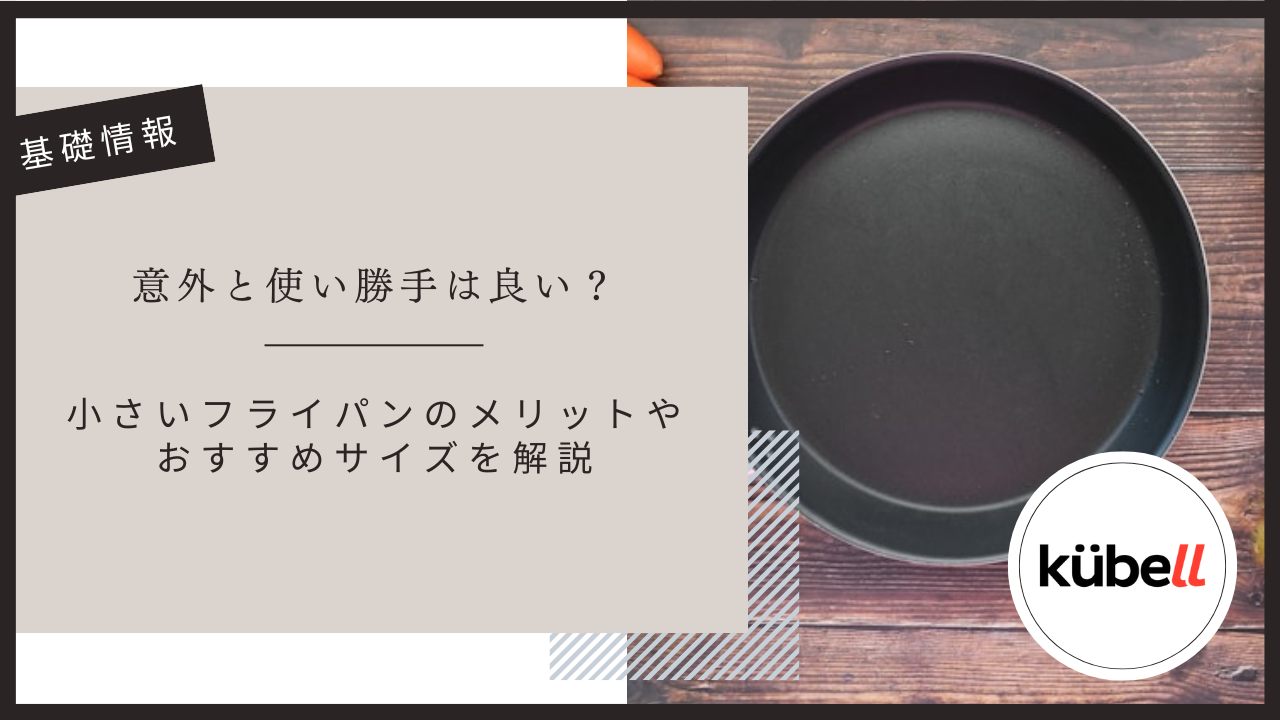
意外と使い勝手は良い?小さいフライパンのメリットやおすすめサイズを解説
「一人暮らしだから小さいフライパンがほしい」「大きいフライパンだけだとフライパンが重いから軽いフライパンがほしい」
小さいフライパンというのは、大きなフライパンと比べて容量が小さいため、1回で作れる料理の量が少なくなるため、一人暮らしに便利です。しかし、小さいフライパンは、一人暮らし以外でも便利に使えるのです。そこで、本記事では、小さいフライパンのメリットやデメリット、選び方を紹介します。
また、一人暮らし・お弁当作りにも便利な小型フライパンをご検討の場合はクーベルのステンレスフライパンをご検討ください。ステンレスは温まりにくく冷めにくい素材なので、食材を入れたあとも温度が下がりにくいという特徴を持っています。加えて、予熱を行うことによって油分を多く含む肉や魚などの食材は無油調理を行うことも可能で、余分な油とカロリーを抑えた健康に良いヘルシーな料理が楽しめます。過去にうまく使いこなせなかった方も、とっつきにくさを感じている方も、ぜひご検討ください!
「小さいフライパン」って実は便利!小さいフライパンのメリット・デメリット
小さいフライパンは、一人暮らしはもちろんのこと、キッチンのスペースを最大限に活用したい方にもおすすめです。一般的には大きさや重さが評価されがちなフライパンですが、小さいフライパンにはたくさんの優れた点があります。そこで、小さいフライパンのメリットやデメリットを紹介します。
1つ目のメリットは、安全性の高さです。というのも、小さいフライパンの軽さは、大きなフライパンと比べて操作しやすいのです。そのため、お子さんやご高齢の方でも扱いやすく、うっかり落とすなどの事故が発生しづらいという特徴があります。加えて小さいフライパンの方が腕への負担が軽減されるため、長時間の使用にも向いています。
2つ目のメリットは、一人前の料理や少量の料理をすぐに作れるという便利さです。加えて小さなフライパンは大きなフライパンよりも熱が均一に伝わるため、短時間での調理が可能です。例えば、忙しい朝の朝食や軽食を素早く準備したいときは、小さなフライパンの方が手軽に作れます。
3つ目のメリットは、最適化しやすい点です。小さいフライパンは、キッチンスペースで邪魔にならず、利用や収納を最大限に有効活用できます。特に狭いキッチンでは、大きなフライパンでは邪魔になってしまう場所であっても問題なく収納可能です。加えて小さいフライパンは大きなフライパンよりも価格が安く、試しに使うのにもぴったりです。
デメリットは、一度に調理できる量が大きなフライパンより小さいため、多量料理には適しません。例えば、大人数分のパスタや煮物を作る場合には適しません。加えて大きな食材を調理する際に、不便に感じるかもしれません。特に大きな魚やステーキを焼く際には、焼くスペースが不足するかもしれません。もう1つのデメリットは、体が大きい人には小さすぎて使いづらく感じるかもしれません。加えてフライパンの小ささが原因で、一部の調理器具が使いづらく感じることもあります。
長く使えるフライパンをお探しなら、クーベルのステンレスフライパンがおすすめです。コーティングがはがれず、適切な使い方で一生モノとして使い続けられます。ぜひ、一度一生モノのフライパンを手にしてみてください。
小さいフライパンを選ぶ際のチェックポイント
フライパンを選ぶ際には、そのサイズや材質、重さなどに注意しましょう。ここでは、最適なフライパンを選ぶためのポイントを紹介します。
サイズ・直径の選び方
最初は、サイズの選び方です。小さいサイズといっても、サイズ・直径は使い方や家族の人数に応じて選ぶ必要があります。最初は、直径を確認しましょう。フライパンの直径は、1回で作る料理の量に影響します。加えてキッチンのスペースや収納場所との兼ね合いも考慮しましょう。考え方としては、直径が小さいほどフライパンの収納が簡単になるかわりに、1回の料理の量が限られます。次に、深さも重要です。基本的な深さの他に、深さが深いフライパンもあります。というのも、料理の種類によっては、浅いフライパンよりも深めのデザインが適している場合があります。例えば、スープや煮物を作る場合には、深さがあったほうが便利です。加えて、深さが十分にあると油はね防止にも役立ちます。とはいえ、深いフライパンは、浅いフライパンよりも収納しづらいため、収納場所を考慮しましょう。
最後は、使用目的です。一人暮らし以外で使う場合、よくあるケースとしては朝食用で小さいフライパンを利用するケースがあります。例えば、朝食用の目玉焼きを焼く場合、大きなフライパンを使うよりも手軽に使え、後片付けも簡単です。加えてお弁当作りなど少量の料理を作りたい場合も、小さなフライパンが活躍します。
最後に、利用人数です。1人暮らしの料理では14cmから16cmが便利ですが、2人以上の場合は少し大きめのサイズを選ぶと良いでしょう。
材質の特徴と選び方
続いて、フライパンで使われる材質の特徴と選び方です。フライパンの材質はアルミや鉄、ステンレスなど多岐にわたります。使われる材質によって、調理や後片付けの簡単さや消耗性に大きな影響を与えます。それぞれの特徴を理解した上で、利用しやすい材質を選びましょう。アルミは、一番普及しているフライパンです。加えて、ほとんどのアルミフライパンでは、フッ素樹脂加工などでフライパンの表面が加工されています。例えば、テフロン加工というのは有名ですが、テフロンもフッ素樹脂の一つです。
アルミの特徴は、熱伝導が優れているため、料理が均一に効率よく仕上がります。加えてフライパンの表面が加工されているため、焦げ付きにくく、油を使わない調理にも適しています。しかし、フッ素樹脂は高温に弱く、強火での調理が苦手です。加えてフッ素樹脂は使っているうちに剥がれるため、定期的な買い替えが必要です。フッ素樹脂とは異なる加工として、セラミック加工があります。セラミック加工はフッ素樹脂加工と似ている性質がありますが、フッ素樹脂よりも環境にやさしいのがメリットです。加えてセラミック加工フライパンは、フッ素樹脂と同様に焦げ付きにくい特徴があります。
中華料理などでおなじみの鉄フライパンは、アルミやセラミックとは異なりフライパンの表面は加工されていません。加えて鉄の性質から硬くて丈夫、高温でも問題なく利用できるため、火力が求められるチャーハンなどと相性が良いです。また、調理した料理には鉄が溶けて鉄分が加わるというメリットもあります。デメリットは後片付けがフッ素樹脂やセラミックよりも大変で、メンテナンスも定期的に行う必要があります。ただし、使い込めば使い込むほど風味に特徴が出てくるため、調理道具を長く使いたい方におすすめです。
最後はステンレスです。ステンレスの特徴は、鉄と同じく丈夫で耐久性が高い点に加え、鉄とは異なりサビに強く鉄製よりもメンテナンスが楽です。加えて保温性が高いため、一度温まってしまえば弱火でもしっかり火が通ります。しかし、熱伝導率が低いため、フライパンがあたたまるまでの時間が長く、予熱をしっかり行う必要があります。ステンレスフライパンは、表面加工がされている製品とされていない製品があります。表面加工がされているフライパンは、表面が焦げづらいかわりに表面加工が剥がれたら交換が必要です。一方で、表面加工されていないフライパンは、表面が焦げやすいため油をたくさん使ってフライパンになじませ、焦げづらくしましょう。
ハンドルの形状・取り外し可否
フライパンのハンドルについても、確認できるようであればしっかり確認しましょう。ポイントは「ハンドルの形状」と「取り外しが可能かどうか」で、使いやすさや収納のしやすさに影響します。ハンドルの形状としては、握りやすいデザインや滑りにくい素材を選ぶと安全性が向上します。特に長時間の調理や重い料理を扱う場合は、握りやすいデザインの方が疲れずに使えます。加えて手の大きさに合っているかも確認しましょう。収納スペースが限られている場合やアウトドアでの持ち運びを検討する場合は、取り外し可能なハンドルが便利です。加えて取り外しがスムーズなものを選ぶと、洗浄時にも便利です。ただし取り外す部分が壊れてしまう可能性があるため、可能であれば口コミなどで頑丈なものを選びましょう。また、取り外せるタイプの場合、ハンドルがしっかり固定されているかどうかも重要です。
最後に、断熱性を紹介します。ハンドル部分が熱くなりにくい素材やデザインを選ぶことで、調理中に発生するやけどなどの事故が防げます。木製やシリコン製のハンドルは断熱効果が高く、鉄などは熱くなりやすい傾向があります。
重さやバランス感
フライパンの重さとバランスは、操作性に直結します。重すぎる場合、非力な子どもや女性などは扱いにくくなります。しかし、軽ければ良いのかと言われるとそうでもなく、軽すぎると逆に不安定になりやすいため、ある程度の重さは必要です。そのため、フライパンを選ぶ際は、適度な重さがあるものを選びましょう。ただし、重いモデルと軽いモデルに迷う場合は、軽いモデルの方がおすすめです。また、軽いフライパンの方が重いフライパンよりも値段が高くなる可能性があるので、注意しましょう。
バランス感とは、主に持ってみたときの重さの感じ方や持ち上げやすさがポイントです。実際にフライパンを選ぶ際に、同じ重さであっても持ち上げやすいフライパンと持ち上げにくいフライパンがあります。重量である程度判断できるものの、実店舗で購入する際は実際に確認するのをおすすめします。
IH・ガス火対応などの熱源対応
最近ではIH対応のフライパンが増えていますが、ガス火専用のものもまだ多く存在します。自宅の熱源に適したフライパンでないと、正しく調理できないので注意しましょう。ガス火を使用している場合、底が厚めで耐久性のあるものがおすすめです。ガス火ならではの火力を活かせる素材を選んだ方が、長い期間活躍できます。IHコンロを使用している場合、底面が平らで磁力に反応する素材のフライパンが必要です。フライパン購入前に、IH対応しているかを必ず確認しましょう。
最近では、ガス火とIHのどちらにも対応しているフライパンも多くあります。例えば転勤などで引っ越しが定期的に発生する場合、引っ越し先で熱源が変わる可能性があります。加えてIHに関しては、別売りでIHコンロを購入する場合もあるため、可能であればどの熱源でも安定して使用できるモデルを選ぶと汎用性が高くなります。アウトドア用のバーナーやキャンプ用の焚き火など、特殊な熱源で使用する場合はそれぞれに対応できるフライパンを選びましょう。
新潟県燕三条市で作られた金属を使用した、クーベルのステンレスフライパンを検討してみませんか。質が高い金属を使用したフライパンなので、半永久的に使い続けられます。ぜひ、この機会に一度クーベルのステンレスフライパンを手にしてみてください。
用途別に見る「小さいフライパン」のおすすめサイズ
用途によって、最適なフライパンのサイズは異なります。ここでは、具体的な使用シーン別におすすめのサイズを紹介します。
一人暮らし向け|14cm~16cmが人気
一人暮らしの方にとって、14cmから16cmのフライパンは非常に便利です。小さいサイズでも十分に使い勝手が良く、必要最低限の量を効率的に調理できます。例えば、朝食の卵焼きや少量の炒め物に最適です。次に、14cm〜16cmのフライパンは収納が簡単です。
小型のため収納場所を取らず、キッチンが狭い環境でも問題ありません。加えて、フックを後付で取り付けて壁に掛けて収納するのもおすすめです。最後に、14cm〜16cmのフライパンは手入れが楽です。一人分の料理を作る場合、大きなフライパンを使ってしまうと後片付けが大変です。小さいフライパンは洗いやすく、お手入れの手間も省けます。
お弁当作り向け|玉子焼き器やスクエア型
お弁当作りには、玉子焼き器やスクエア型のフライパンが活躍します。形状が決まっているため、特定の料理を作るのに最適です。玉子焼きようフライパンは、均一な厚みで美しい玉子焼きを簡単に作れます。特に初心者でもきれいに仕上げられるため、お弁当作りが楽しくなります。スクエア型は、お弁当用の小さな食材を調理するのに便利です。例えば、小さなハンバーグや焼き野菜などが効率的に作れます。お弁当用には焦げ付きにくい加工が施されたものを選ぶと、短時間で調理が可能です。サイズ感としては、玉子焼き器は横幅が広めのものもありますが、収納や持ち運びを考慮してコンパクトなものを選ぶのがおすすめです。
キャンプやアウトドア向け|コンパクトかつ軽量モデル
キャンプやアウトドアでは、持ち運びやすいフライパンがおすすめです。小さいフライパンは荷物を軽減しつつ、アウトドアで必要な調理が可能です。その中でも軽量モデルは持ち運びやすく、アウトドアでの使用に最適です。特にバックパックに収納する場合は、全体の荷物の重さが体力に直結するため、なるべく軽いモデルを選びましょう。次に、キャンプなどでは過酷な環境に晒されるため、外で使うため家の中よりも壊れやすくなります。
そのため、アルミニウムやステンレス製などの耐久性が高い素材であれば丈夫で長持ちします。アウトドア用のフライパンでは、フライパンを使い分けづらいので、蓋付きのものやスキレットタイプもおすすめです。一台で煮る・焼く・炒めるが可能なものを選ぶと重宝します。最後に、折りたたみ式のハンドルや収納袋が付属しているものを選ぶと、荷物をコンパクトにまとめられます。
美味しく調理できるフライパンをお探しの場合は、クーベルのステンレスフライパンを検討してみませんか。保温性が高く、汎用性も高いフライパンで簡単に美味しい料理を作れます。ぜひ、この機会に一度クーベルのステンレスフライパンを手にしてみてください。
長持ちさせるためのメンテナンス・お手入れ方法
フライパンを長く使うためには、適切なメンテナンスが欠かせません。そこで、長持ちさせるために必要な手入れ方法やポイントを紹介します。
素材別メンテナンスポイント
フライパンの材質によって、お手入れの方法は異なります。それぞれの特徴を理解して、適切にケアしましょう。アルミフライパンでフッ素樹脂やセラミック加工されているフライパンの場合は、柔らかいスポンジで洗います。金たわしなどや、金属製の調理器具の使用は避けましょう。急激な温度変化も表面のコーティングが剥がれてしまう原因になるため、熱々のフライパンを冷やすために冷水で冷ますや、油を取るために熱湯をかけるのもよくありません。
鉄フライパンの場合は、洗剤はあまり使わずに金たわしなどで焦げやサビをしっかり落としましょう。加えて洗った後に油をフライパンに塗ることで、サビを防ぎます。ステンレスも鉄と近い洗い方になりますが、サビづらいので洗浄した後に油を塗る必要はありません。焦げ付きが発生した場合は、重曹やクエン酸を使ったお手入れがおすすめです。
洗い方・保管のコツ
フライパンを洗う際には、以下の点に注意しましょう。最初のポイントは洗剤です。材質に合った洗剤を使用した上で、しっかりすすいで洗剤がフライパンに残らないようにしましょう。特にフライパンの表面がフッ素樹脂などでコーティングされている場合は、研磨剤の入った洗剤はコーティングが剥がれる原因になるため使用は控えましょう。鉄フライパンの場合、可能であれば洗剤は使わずにしっかり洗うことで、フライパン自体が成長していきます。
きれいに洗った後は、洗った後はしっかりと乾かしてから保管します。というのも、水分が残るとサビついてしまう可能性があります。特に鉄製フライパンは、サビつきやすいため注意が必要です。収納する場合、可能であれば重ね置きしない方がおすすめです。とはいえ収納スペースがあまり取れない場合は、フライパンとフライパンの間に布などを挟むことで、コーティングなどが長持ちします。もしハンドルにフック穴がある場合、吊り下げて保管する方法があります。吊り下げの場合は、フライパンが乾燥しやすくなりますし、フライパンが重ならないのでおすすめです。
寿命の目安と買い替え時期
フライパンの寿命は、材質や使用頻度によって異なります。フライパンの表面がフッ素樹脂などでコーティングされている場合は、表面のコーティングが剥がれてきたら買い替え時です。目安として1〜2年程度、長くても3年くらいで寿命を迎えます。鉄フライパンの場合、適切に手入れすれば長く使えます。ただし、ひび割れや深いサビが発生したら買い替えを検討しましょう。ステンレス製は鉄フライパンよりもメンテナンスが楽で長持ちしますが、焦げ付きや変色が目立つようになった時期が買い替えるタイミングです。
全体的に言えることは、フライパンの底が歪んだなど熱が均一に伝わらなくなった場合は新しいものに交換しましょう。お手入れ簡単で長持ちするフライパンをお探しなら、クーベルのステンレスフライパンを検討してみませんか。調理面がコーティング加工がされておらず、ゴシゴシ洗えるためお手入れが楽ちんです。ぜひ、一度クーベルのステンレスフライパンを手にしてみてください。
よくある質問(Q&A)
小さいフライパンに関するよくある質問を、インターネットを中心に調査しました。小さいフライパンを購入する際は、ぜひ参考にしてくださいね。
Q1. 小さいフライパンの容量はどれくらい?
フライパンの容量は、サイズによって異なります。例えば、14cmのフライパンは約0.5リットル程度の容量です。ただし、深さによっても容量が変わるため、実際に購入したいフライパンの容量を確認しましょう。容量を重視したい場合は、深めのデザインを選びましょう。深さがある方が煮込み料理や汁物など、レパートリーが増えます。
Q2. 小さいフライパンの寿命は?
小さいフライパンの寿命は、大きなフライパンの寿命とほとんど変わりません。フライパンの表面がコーティングされている場合は、1〜2年程度です。鉄やステンレスの場合は、利用頻度やお手入れの仕方によっては一生涯使える場合もあります。ただし、落とすなどしてフライパンが変形してしまった場合などは買い替えを検討しましょう。
長く使えるフライパンをお探しなら、クーベルのステンレスフライパンがおすすめです。コーティングがはがれず、適切な使い方で一生モノとして使い続けられます。ぜひ、一度一生モノのフライパンを手にしてみてください。
まとめ
小さいフライパンは、コンパクトで使い勝手が良い便利なアイテムです。一人暮らしや少量調理、アウトドアでの使用など、さまざまなシーンで活躍します。選ぶ際にはサイズや材質、熱源対応などをしっかりチェックし、適切にメンテナンスすることで長く愛用できます。ただし、小さいフライパンだけだとデメリットもあるため、少し大きめサイズのフライパンを用意しておくと便利です。クーベルのステンレスフライパンは、24cmと27cmがあります。小さいフライパンとセットで用意するのにおすすめしたいのは24cmで、16cm前後のフライパンと24cm程度のフライパンを持っていれば、たいていの料理は作れます。
クーベルのステンレスフライパンは、ステンレスのメリットである丈夫さや保温性の高さはそのままに、ステンレスとアルミの三層構造のため、一般的なステンレスフライパンよりも軽く、加えて熱伝導率が上がっています。そのため、一般的なフッ素樹脂加工フライパンと同じように扱えます。最後になりますが、自分に合った小さいフライパンを見つけて、快適な料理時間を楽しみましょう。現在クーベルでは30日間の全額返金保証に対応しています。クーベルのフライパンが気になるという人は、ぜひこの機会に試してみてください。