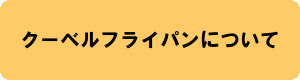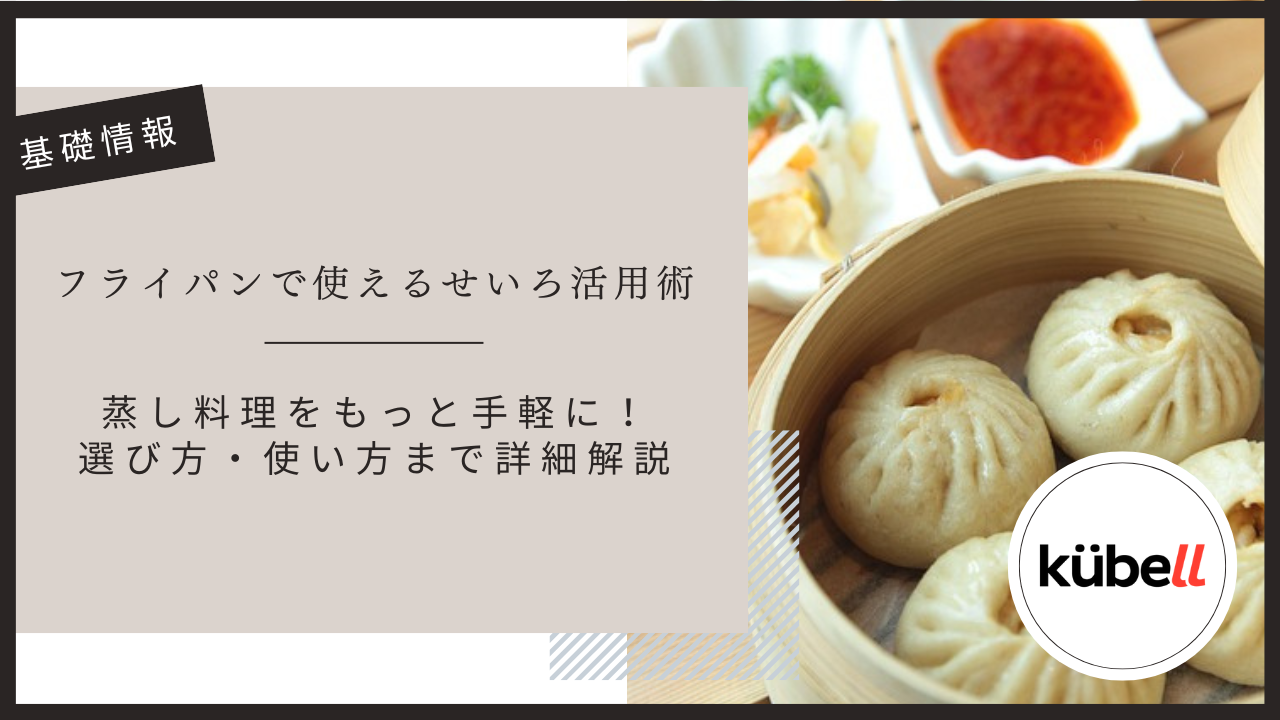
フライパンで使えるせいろ活用術|蒸し料理をもっと手軽に!選び方・使い方まで詳細解説
「フライパンとせいろを組み合わせた調理が流行っていると聞いたけど」
「フライパンと一緒に使える調理道具を教えてほしい」
フライパンとせいろを組み合わせた調理法が、今多くの家庭で注目を集めています。
せいろと聞くと、専用の蒸し鍋や大きな中華鍋が必要だと思われがちですが、実際には一般的なフライパンでも十分に活用できます。
本記事では、フライパンで使えるせいろの活用術を紹介していきます。
また、ステンレスライパンをご検討の場合はクーベルのステンレスフライパンをご検討ください。
ステンレスは温まりにくく冷めにくい素材なので、食材を入れたあとも温度が下がりにくいという特徴を持っています。加えて、予熱を行うことによって油分を多く含む肉や魚などの食材は無油調理を行うことも可能で、余分な油とカロリーを抑えた健康に良いヘルシーな料理が楽しめます。
ぜひこの機会に、一生モノのフライパンをお手に取ってみてください。
はじめに|フライパン×せいろが人気の理由
フライパン×せいろの組み合わせは、忙しい現代人の食生活にぴったりの調理スタイルとして、多くの家庭で取り入れられています。
例えば定番の肉まんやシュウマイはもちろんとして、蒸し料理やヘルシー料理にも活用できます。
蒸し料理は、食材の栄養や旨みを逃さず、油を使わないためとてもヘルシーです。
そのうえ、後片付けも簡単で、時短調理にもつながります。
そこで、フライパンでせいろを使うための基本知識から、選び方、実践的なレシピ、注意点、よくある質問まで、幅広く詳しく解説します。
せいろ初心者の方も、日々の献立に新しいバリエーションを加えたい方も、ぜひ参考にしてください。
フライパンでせいろを使う基本知識
フライパンにアルミフライパンやセラミックフライパンなど様々な製品があるように、せいろにも様々な種類が存在します。
加えて、せいろならではの使い方や注意点などがあります。
そこで、せいろについての基礎知識を紹介します。
せいろとは?素材の種類(竹・木・ステンレス)
せいろは、蒸気の力で食材を加熱する伝統的な調理器具で、日本や中国などアジア圏で古くから使われてきました。
主な素材には竹や杉、ひのきなどの天然素材と、ステンレスやアルミニウムといった金属製があります。
竹や杉のせいろは、蒸しあがりに木の香りがほんのり移り、食材がふっくらと仕上がるのが特徴です。
天然素材のせいろは、例えば和食や中華料理の点心など香りを楽しみたい料理に向いています。
天然素材の中でもひのきは耐久性が高く、長時間の蒸し料理にも適しています。
木製せいろは吸水性があるため、余分な水分を吸い取り食材がべたつきにくいというメリットもあります。
一方、ステンレスやアルミのせいろは、熱伝導が良く、均一に加熱できるうえ洗剤でしっかり洗えるのでお手入れが簡単です。
加えて金属製はカビや臭い移りの心配が少なく、衛生的に使える点も魅力です。
素材によって蒸しあがりの風味や扱いやすさが異なるため、用途や好みに合わせて選ぶことが大切です。
フライパンでせいろを使うときの注意点
フライパンでせいろを使う際には、いくつかの注意点があります。
せいろの焦げ付きや食材のにおい移り、乾燥による割れを防ぐために必ず水で濡らしてから使用しましょう。
フライパンで使う際は、フライパンに十分な量の水またはお湯を入れ、蒸気がしっかり上がる状態でせいろを乗せます。
フライパンの水が少ないと空焚きになってしまい、せいろやフライパンが傷む原因となります。
蒸し時間が長い場合は蒸し途中で水が減らないよう、こまめにチェックし必要に応じて熱湯を追加してください。
せいろの底が水に直接触れないよう、蒸し板や鍋敷きを使うとさらに安全です。
せいろのフタを開ける際は、熱い蒸気が一気に立ち上るため、やけどしないよう顔や手を近づけすぎないよう注意しましょう。
蒸し板(中華鍋リング)・鍋敷きの使い方
フライパンとせいろのサイズが合わない場合やせいろの底が水に浸かってしまう場合は、蒸し板や中華鍋リングの活用が効果的です。
蒸し板とは、フライパンの上に置いてせいろを安定して乗せるための道具です。
蒸し板を置くことで、せいろが水に直接触れることなく蒸気だけで加熱できます。
中華鍋リングは、せいろとフライパンの隙間を埋めて安定させる役割を果たします。
鍋敷きを使う場合は、耐熱性のあるものを選び、せいろの底が水面から2cm程度浮くように調整しましょう。
蒸し板や鍋敷きは、異なるサイズのフライパンでもせいろを活用できます。
加えてせいろの焦げ付きや変形も防いでくれるため、長くせいろを愛用したい方におすすめです。
フライパンでせいろを使うメリット・デメリット
続いて、せいろで中華鍋を使わずにフライパンを使うメリットとデメリットを紹介します。
せいろが中華鍋で使うのが面倒な人は、とくにフライパンで使うメリットを確認いただき活用しましょう。
メリット|手軽・後片付けが楽・時短調理も可
フライパンでせいろを使う最大のメリットは、手軽さと汎用性にあります。
というのも、専用の蒸し鍋を用意しなくても、普段使っているフライパンがそのまま使えるため特別な道具を揃える必要がありません。
加えてせいろは構造がシンプルで洗い物も少なく、後片付けが簡単です。
例えば木製せいろの場合、洗剤を使わず軽く水洗いするだけで清潔に保てます。
さらに、せいろを重ねて複数の食材を同時に蒸せば、主菜と副菜を一度に調理でき、時短調理も実現できます。
例えば、下段でごはんやもち米、上段で野菜や肉まんを同時に蒸すことも可能です。
蒸し料理は冷めても美味しく、お弁当や作り置きにも向いています。
フライパンとせいろの組み合わせは、忙しい毎日の食事作りをサポートしてくれる強い味方です。
デメリット|サイズ制限・水切れ・フタの扱いに注意
残念ながら、フライパンでせいろを使う際のデメリットもあります。
1点目は、一度に蒸せる量に限界がある点です。
家庭用のフライパンではせいろのサイズが限られるため、大人数分を一度に調理する場合は何回かに分けて蒸す必要があります。
次に、フライパンの水が少なくなると空焚きのリスクがある点です。
空焚きしてしまうと、せいろやフライパンが傷む原因になります。
特にIHコンロの場合は加熱が早いため、蒸し時間が長くなる料理や厚みのある食材は、途中で水を追加する手間がかかります。
最後に、せいろのフタを開ける際は熱い蒸気に注意しなければなりません。
加えて布きんを巻かないと水滴が食材に落ちてしまい、仕上がりが水っぽくなることもあります。
フライパンでせいろを使う注意点を理解し適切に対策を取ることで、せいろ調理のデメリットを最小限に抑えられます。
フライパンで使えるせいろの選び方
フライパンでせいろを使うメリットとデメリットを理解いただいたところで、フライパンで使うせいろの選び方を紹介します。
蒸し鍋とはサイズが異なるので、フライパンに合うせいろを選ばないと使い物にならない可能性があります。
気に入ったせいろがあった場合は、フライパンに合うかどうか確認してから購入しましょう。
サイズ(18cm〜24cm)の選び方と目安
せいろのサイズ選びは、フライパン調理の快適さを左右します。
家庭用フライパンで使う場合、18cmから24cm程度のせいろが一般的です。
フライパンが大きすぎるとせいろが水に浸かってしまい、小さすぎるとせいろが直接火に当たって焦げる恐れがあります。
せいろは重ねて使うこともできるため、家族の人数や用途に合わせて複数サイズを揃えておくと便利です。
フライパンの内径とせいろの外径の関係
フライパンでせいろを使う際は、フライパンの内径とせいろの外径のバランスが非常に重要です。
せいろがフライパンにしっかり乗るサイズであることと、せいろの底が水に浸からない高さを確保できることがポイントになります。
せいろの直径は、フライパンの内径より1〜2cm小さいものが理想です。
例えば、24cmのフライパンには22cmのせいろが安定して乗ります。
せいろの底が水面から2cm程度浮くように調整すると、蒸気がしっかり食材に伝わり、せいろの焦げ付きも防げます。
せいろの外径がフライパンの内径より大きいと、フタがきちんと閉まらず蒸気が逃げてしまうので注意してください。
もしサイズが合わない場合は、蒸し板や中華鍋リングを使って高さや安定感を調整しましょう。
素材ごとの特徴とメンテナンス性
せいろの素材によって、使い心地やお手入れの方法が大きく異なります。
杉や竹のせいろは軽くて扱いやすく、蒸しあがりに木の香りが移るのが魅力です。特に竹せいろは通気性が良く、余分な水分を吸収して食材がべたつきにくいです。
ひのきのせいろは耐久性が高く、長時間の蒸し料理にも適しています。
ステンレスやアルミのせいろは熱伝導が良く、お手入れも簡単です。洗剤でしっかり洗えるので、衛生的に使えます。
金属製はカビや臭い移りの心配が少なく、長く使いたい方や頻繁に蒸し料理を作る方におすすめです。
フライパンも、蒸し焼きが得意でメンテナンス性が高いステンレスフライパンがおすすめです。
クーベルのステンレスフライパンは、保温性が高いステンレスフライパンの特徴はそのままに、多層構造で熱伝導率を高めています。
フライパン×せいろで作るおすすめレシピ
フライパンでおすすめしたいせいろを紹介したあとは、実際のレシピを紹介します。
定番料理からせいろならではの料理まで、4つのレシピを紹介します。
定番の肉まん・シュウマイ・小籠包
せいろといえば、肉まんやシュウマイ、小籠包などの点心が定番です。
せいろで蒸すことで、生地がふっくらと仕上がり、中の具材もジューシーに蒸しあがります。
肉まんは、発酵させた生地で具材を包み、せいろで蒸すことで独特のもっちり感が生まれます。
シュウマイや小籠包は、せいろの蒸気で皮がしっとりとし、中から肉汁が溢れ出す本格的な味わいが楽しめます。
せいろで蒸すときのコツは、クッキングシートや蒸し布巾を敷いておくと、皮がくっつかず後片付けが簡単です。
フライパンならではの使い方としては、市販の冷凍点心であってもせいろで蒸すだけでお店のような仕上がりになります。
野菜の蒸し料理(ブロッコリー・かぼちゃなど)
ブロッコリーやかぼちゃなどの野菜も、せいろで蒸すことで素材本来の甘みや食感が引き立ちます。
蒸し料理は油を使わず調理できるため、ヘルシーな副菜として重宝します。
ブロッコリーは小房に分け、かぼちゃは薄切りにしてせいろに並べます。
せいろに並べる際は、蒸気の通り道を確保することがポイントです。
蒸した野菜はそのまま食べても美味しいですが、塩やオリーブオイル、ポン酢などで味付けすれば、さらにバリエーションが広がります。
ごはんやもち米の蒸し方
せいろはごはんやもち米を蒸すのにも適しています。
もち米は一晩水に浸してから、蒸し布巾を敷いたせいろに広げます。
蒸し時間はもち米の場合40分程度が目安のため、途中で水がなくならないようフライパンの水量に注意しましょう。
白米や雑穀米も、せいろで蒸すことで粒が立ちもちもちとした食感が楽しめます。
せいろで蒸したごはんは、冷めても硬くなりにくく、おにぎりやお弁当にも向いています。
魚の酒蒸し・ヘルシー料理の幅を広げよう
魚の酒蒸しやヘルシーな蒸し料理も、フライパン×せいろの組み合わせで簡単に作れます。
簡単な作り方としては、魚に酒や調味料をふりかけてせいろに並べて蒸し上げるだけで、ふっくらとした仕上がりになります。
魚と一緒に野菜やきのこを蒸せば、栄養バランスの良い一品が完成します。
加えて、せいろであれば油を使わないヘルシー料理が手軽に作れます。
例えば、鶏肉や豚肉、豆腐などもせいろで蒸すことで、油を使わないことに加えて余分な脂が落ちてヘルシーに仕上がります。
フライパンでせいろを使うときのポイント
フライパンとせいろを使った得意料理を紹介したところで、フライパンでせいろを使うときのポイントを紹介します。
ポイントを押さえないと料理が失敗してしまう可能性があります。
水の量と火加減の調整方法
フライパンでせいろを使う際は、水の量と火加減の調整が重要です。
というのも、水が少ないと空焚きになりやすいため、蒸し時間が長い場合は多めに水を入れましょう。
フライパンの深さにもよりますが、目安としては底から2cm程度の水を入れておくと安心です。
最初は強い火で蒸したあと、蒸気がしっかり上がったら中〜弱火にして問題ありません。
さらに、水が入っているかを定期的に確認し、途中で水が減ったら熱湯を追加します。
火加減は、蒸気がしっかり上がる程度を目安に調整します。
蒸し料理は加熱ムラが出にくいですが、途中でせいろの位置を少し回すと、さらに均一に仕上がります。
せいろが焦げないための注意点(濡れ布巾・クッキングペーパー)
せいろが焦げ付かないよう、使用前に全体を水で濡らしておき、特に底部分はしっかりと水分を含ませましょう。
食材を直接置く場合は、クッキングシートや蒸し布巾を敷くと、せいろが汚れにくく、焦げ付きも防げます。
せいろの底がフライパンの熱源に直接触れないよう、蒸し板や鍋敷きを使うのも効果的です。
フタの蒸気対策(布きんを巻く理由)
せいろのフタに布きんを巻くと、蒸気が水滴となって食材に落ちるのを防げます。
蒸し料理では、フタの内側に水滴がたまりやすく、そのままでは料理が水っぽくなってしまいます。
布きんが余分な水分を吸収することで、料理がべたつかず、仕上がりがきれいになります。
注意点は、フタを開ける際は布きんが熱くなっているので、やけどに注意してください。
ステンレスフライパンは、一度蒸気があがってしまえば弱火で調理できます。
クーベルのステンレスフライパンの浅型サイズは、サイズが24cmとちょうど良いサイズです。
よくある質問(Q&A)
フライパンで使えるせいろについて、インターネットを中心によくある質問を調査しました。
フライパンでせいろを使いたい人は、ぜひ参考にしてください。
Q1. フライパンの上にせいろを直接置いても大丈夫?
フライパンの上にせいろを直接置いても問題ありませんが、せいろの底が水に浸からないよう注意が必要です。
水位が高いとせいろが濡れすぎてしまい、低すぎると空焚きのリスクがあります。
蒸し板や中華鍋リングを使うと、せいろが水面から浮き、安定して安全に蒸せます。
せいろを乗せる前に、フライパンの水量を確認し、せいろが安定しているかどうかチェックしましょう。
Q2. IH対応のフライパンでも使える?
はい、IH対応のフライパンでもせいろは使えます。
ただし、IHは加熱が早いため、水が蒸発しやすくなります。
そのため、水量をこまめにチェックし、必要に応じて追加しましょう。
加えて、IHコンロの場合はフライパンの底全体が均一に加熱されるため、せいろの底が焦げやすくなることがあります。
せいろの底をしっかり濡らし、蒸し板や鍋敷きを使って底が直接熱源に触れないようにするのがポイントです。
Q3. アルミやステンレスのせいろでも使い方は同じ?
アルミやステンレス製のせいろも、基本的な使い方は木製と同じです。
金属製は木製よりも熱伝導が良く、短時間で均一に加熱できます。
加えて洗剤でしっかり洗えるため、衛生的に使えるのもメリットです。
デメリットは金属製せいろは蒸気を逃がしにくく、食材が水っぽくなりやすい傾向があります。
そのため、蒸し時間や火加減に注意し、蒸気がこもりすぎないようフタを少しずらして蒸すのも1つの方法です。
鉄製せいろはカビや臭い移りの心配が少なく、手軽に使える点が魅力です。
まとめ|せいろをフライパンで手軽に楽しもう!
本記事では、フライパンで使えるせいろ活用術を紹介しました。
せいろは専用鍋がなくても、フライパンで手軽に楽しめます。
フライパンだけでも蒸し料理は可能ではありますが、せいろを使うことで木の香りを重ねることで味に深みが広がります。
せいろにおすすめしたいフライパンは、クーベルのステンレスフライパンです。
クーベルのステンレスフライパンの中でも、24cmの定番フライパンは、22センチサイズのせいろにちょうど合います。
クーベルのステンレスフライパンは、保温性と熱伝導率の高さでせいろを使った調理に優れています。
加えてクーベルのステンレスフライパンは後片付けやメンテナンスが楽で、通常使いのフライパンとしてもおすすめです。
大切に使えば一生涯使えるクーベルのステンレスフライパンを、ぜひご検討ください。